厳しい様で前向きな心理学
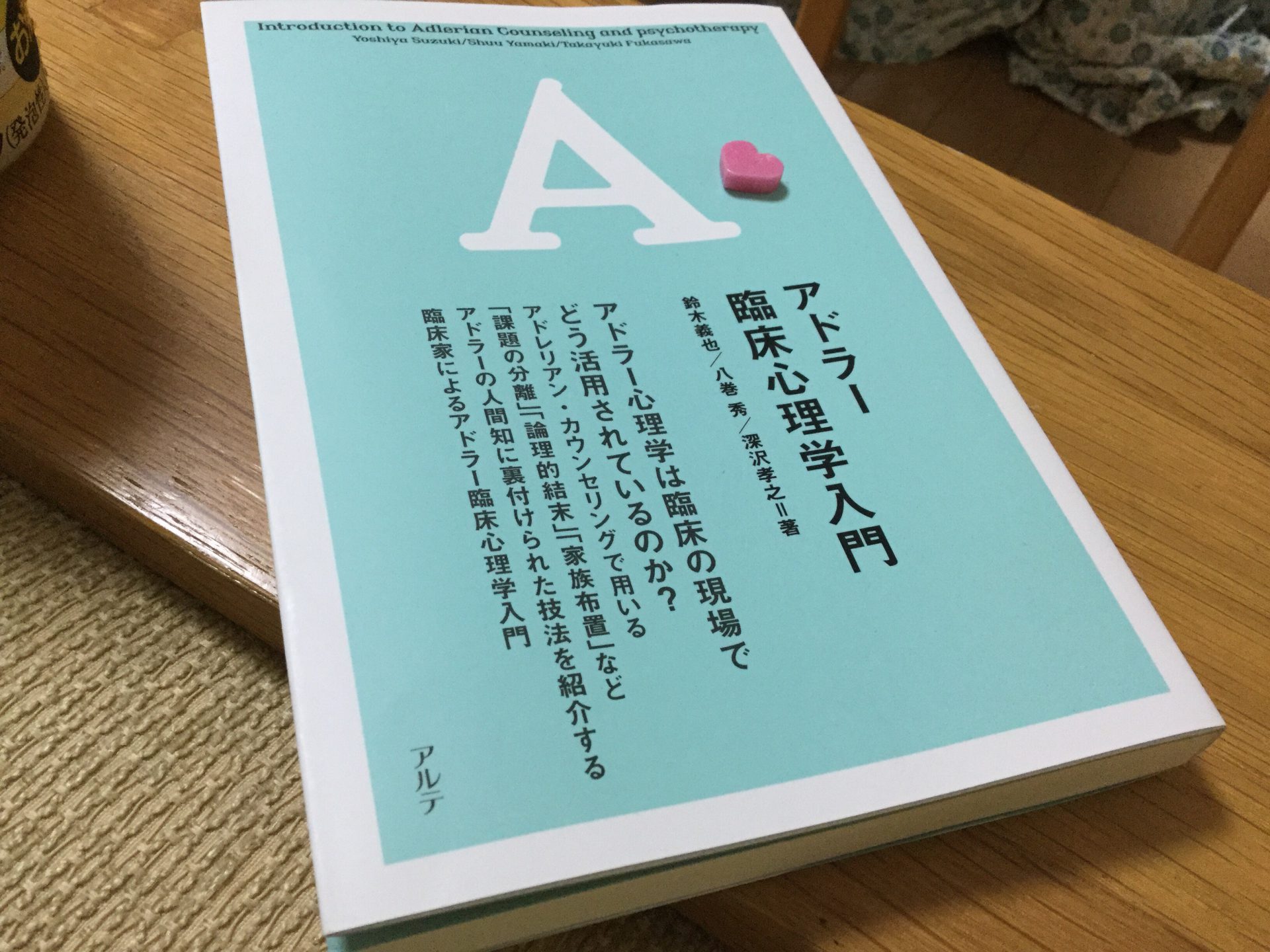
「うっざ!」
私の学生時代における、心理学を専攻する方々に対する感情です。目の前にある現象に名前を付けて、わかったように語る。同じ事象を、まったく別の視点から分析して、まったく異なる結論に至り、それを真顔で延々と、淡々と語る。分析したところで、そしてそれを語ったところで、誰も救われない。むしろ下手すると相手を追い詰めて、余計に身動きがとり辛い状態にしてしまう。心理学から得られる発展はないと、強い嫌悪感さえ抱いておりました。
拒絶するのはオーバーリアクションだとは思いますが、決め付けられることがどれほど嫌なことかを、体験させてくれたことは事実です。いまでも、自分が他人のことを決め付けようとするときに、どこか後ろめたい気持ちにさせてくれたのは、当時に同じことをやられた時の拒絶の感情を経験しているから、とも言えなくもないからです。いや、アドラー的に考えると、自分は他人を決め付けないという人生を歩むことを決めたから、道から逸れないために当時の拒絶の感情を思い出している、ということなのでしょうか。
[amazonjs asin=”4434204890″ locale=”JP” title=”アドラー臨床心理学入門”]
アドラー?
近年着々と人気になっているアドラー心理学ですが、まだご存じない方や、「ああ、名前は聞いたことある」という方も多いのではないでしょうか。一言でいうと、原因ではなく、目的に重きを置いた心理学です。過去ではなく、今。むしろ過去の記憶という概念さえも、「ちょっと違うぞ」と。記憶は「今、ここにあるものである」と言うのです。目的論と原因論という大きな考え方の違いとして整理されますが、本の中にわかりやすい例があったのでここで引用してみます:
原因論の問い「花子さんは何で、学校に行かないのでしょうか」
目的論の問い「花子さんは何のために、学校に行かないのでしょうか」
はじめて「目的論」の概念に触れる方々は、いまいちこの違いにぴんとこないかも知れませんが、この二つの考え方では、見えてくるものが全くことなります。どちらも「why」の問いであると言う意味では同じですが、原因論の問いは過去に向いているのに対して、目的論の問いは目標に向いています。先の自分の体験を原因論と目的論でそれぞれ分析すると:
原因論:「過去に決めつけられて嫌な思いをしたから、自分も他人を決めつけると当時の感情を思い出して後ろめたくなる」
目的論:「他人のことを決めつけないと決めた、だから決めつけそうになったら、当時自分が嫌な思いをしたことを思い出して、自分を制する」
ということでしょうか。自分を「自分が考えた最強のオランダ人」という理想に近づけるために「負の記憶」を利用しているということです。ある意味、心理学を専攻されていた方々はとんだとばっちりですが…
優しい本
アドラーは、「嫌われる勇気」(ダイヤモンド社刊)の出版により日本で一般的に広く認知されるようになりました。私も楽しく読ませていただきましたが、「嫌われる勇気」は少々強引なところがあり、一切の予備知識も無しに読むと「いままでの人生観を全否定されている…」と言うような気分になることも考えられます。会話形式で話が進むのですが、頑固な若者と悟った哲学者の間で激しい言葉の応酬が行われるため、斜め読みしてしまうと「アドラーって正論言うけど何とまー冷たい」と勘違いしてしまいそうです。
反面、本書は「嫌われる勇気」よりちょこっと難しいですが、優しく引っ張ってくれます。難しい部分も、臨床心理学用語がふんだんに使われる本の一部分のみですし、完全には理解できなかったのですが、本の残りを理解するのに支障は無かったです。本の「優しさ」ですが、さすがにカウンセラーさんが書いた本だけあって、まるで読者がカウンセリングを受けているような気分にさえなれます。まず、良いと思ったのが、認知論について最初の方でしっかり説明しているからです。アドラー原著の「Understanding Human Nature」でも、ここをしっかりレクチャーしているので、おそらくアドラーの考え方を理解する上では大事な土台だと思われます。
我々は状況をそれ自体として経験することはない
つまりは、あの有名なあれです。ダニは哺乳類の血液をご飯とします。ダニの嗅覚は哺乳類が決まって放出する酪酸を敏感に嗅ぎ分け、運を天に任せて匂い=哺乳類めがけて決死のダイブを行う。そして血をたらふく食べて、次の世代へと繋げます。ダニにとって酪酸は哺乳類と同義であり、酪酸を嗅ぎ分けることは生きるための手段です。ライオンにとっても、びっこ引いてるレイヨウがご飯で、それ以外はご飯に辿り着く上での障害物です。人間も、こういった意味づけの世界に身を置いていることを(改めて、何度でも)認識することは、アドラー心理学で言う劣等感、家族布置、共同体感覚等の理解を深める上で大事だと感じました。
おすすめ?
お勧めです。読みやすいし、各章の末尾に参考文献・引用文献も載せているので、ここから色々と勉強が捗りそうです。上司や部下、お客さん等、人間関係にお悩みの方にも、特にお勧めしたいです。そこらの教条的な自己啓発本よりずっとためになると思います。また、著者がカウンセラーということだけあって、例示も現実味のあるもので、大変参考になりました。

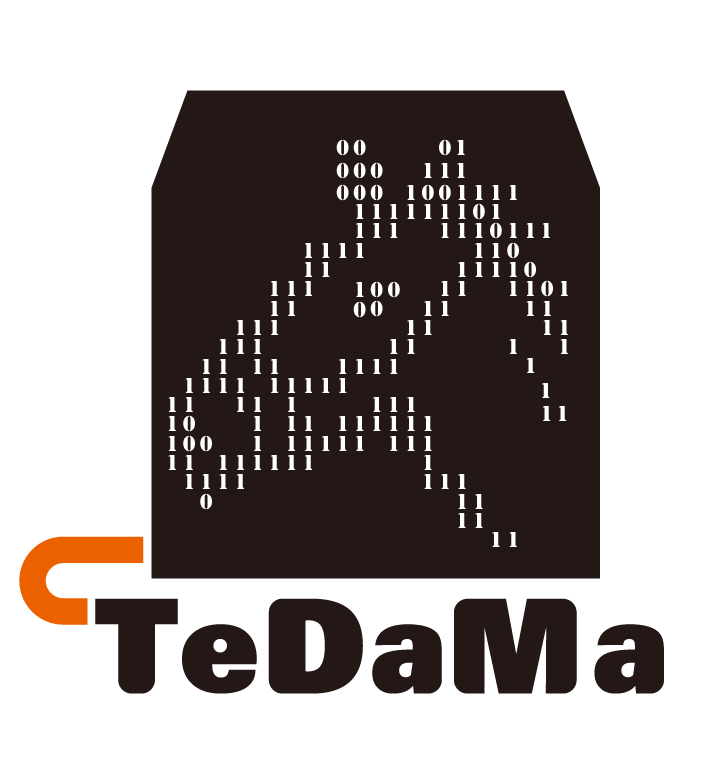
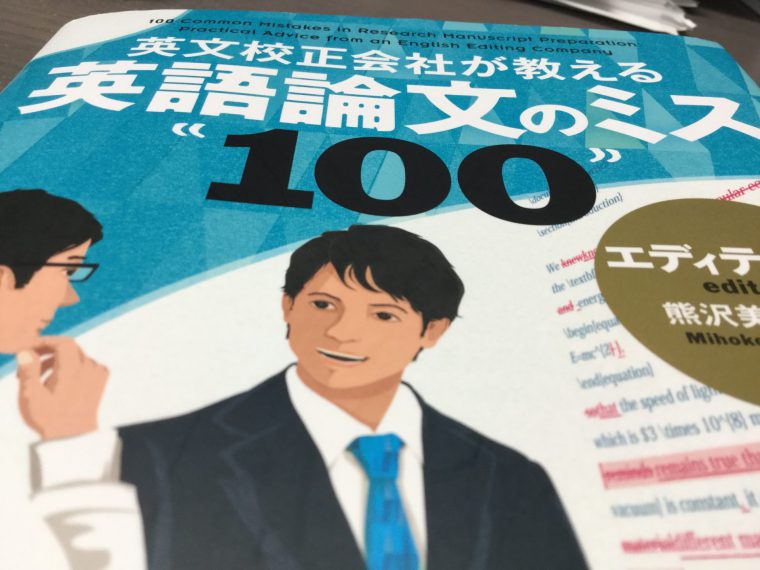
コメント