バリデーション如何でしょうか?

日本にきて最初の就職先は、一つのビルの中にSMOとCROとクリニックが全部つまっているとあるグループ会社でした。カルチャーショックのオンパレードが待ち受けているとも知らずに、(頭の中的に)生粋のオランダ人が日本企業に足を踏み入れてしまったのです。そして出会いました…データの目視チェックという業務に。
中小のCROに勤務されていた方々は、僕と同じようにここで頭を抱えて色々なことを思い出して苦笑いするのだと想像しますが、そうでない方々も読まれているかも知れないので、一応説明します。目視チェックとは、その名の通り、目でチェックをするわけです。例えば、検査会社からもらった生データの大きな表があったとします。この表には全被験者のデータが載っているのですが、これをデータマネジメントソフトで意味のある形に並び替えてまた出力します。例えば、一回目の来院の血液データのみで、列に被験者番号、行に各検査項目、と言ったように。データの目視チェックは、加工の前と後とでデータが全く同じであることを確認する作業です。そして、確認したマスにはレ点を打っていきます。
全部。
一日に数千のレ点を打つなんてザラです。20*20マスの表が、赤ボールペンのレ点でいっぱいになります。マス目ばかり見ているので、目がおかしくなりそうです。終わったら、次はダブルチェック担当に回ります。そしてまた目視チェックしながら、別の色でレ点を打ちます。うっかり同じ色で打ってしまったことがあり、発注者に問い合わせてみたら無慈悲にも「やり直して~」と言われ、スタッフ総出でテーブル囲んでひたすらレ点を打っていたこともありました。ボールペンを握る手の中指に、痣にも見える(数日は消えない)変色が出来ていました。
読み合わせというバリエーションもあります。成果品が前述のレ点ぎっしり表という意味では同じなのですが、一人で目視チェックするのではなく、二人一組で読み上げ担当とレ点担当に分かれます。こちらはまだ救いがありました。やっているうちに、何も「52.739」というデータをわざわざ「ゴジュウニーテンナナサンキュウ」と読み上げなくても、「ゴニテンナミク」と読み上げれば良いと気づいたからです。最初は皆さん消極的でしたが、読み合わせにかかる時間が半減できることがわかると、徐々に皆が「フランク法」を取り入れる様になってくれました。脱線失礼。
今なら、プロセスを一回バリデーションすれば良い話なのですが、当時はまだコンセンサスがなかったのでしょう。念のために言っておきますが、当時はバリデーションもやっていました。データマネジメントソフトに取り込むためのコードも、加工するコードも、別々の人が二重で組んで、結果が同じであることを確認していました。どうせレ点を打つ羽目になるのに…と思われるかも知れませんが、バリデーションをしっかりやらないと、レ点地獄のやり直しが待っているかも知れないからです。バリデーションをする理由はズレていたかも知れませんが、定時退社と精神崩壊を分かつほど重要なものだったので、必死でした。

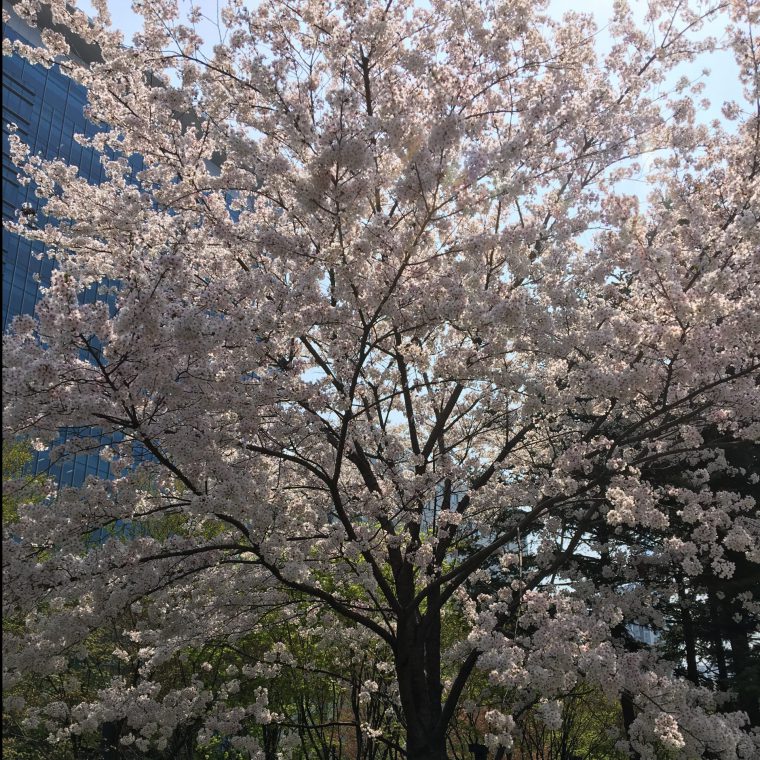



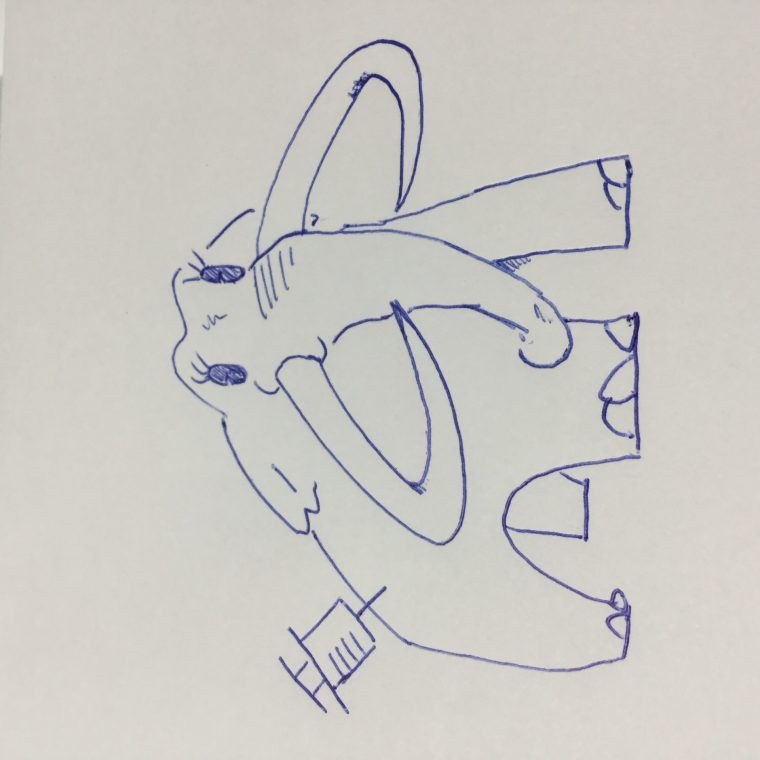



コメント