マンモス型臨床研究
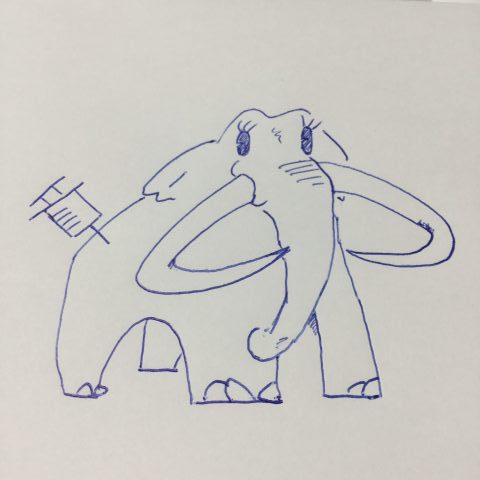
何百例、何十施設を巻き込んだ多施設共同研究がやりたいけど、紙の調査票に書き込んでもらって、事務局などの特定の箇所に集めてもらって、そこで電子化して、解析して…というのは、誰もがイメージできると思いますが大変なことです。EDCが使える!となると、皆さん期待が一斉に膨らみます。各施設でシステムに入力してもらって、自動的に一箇所にデータが集積される…素晴らしいことです。便利が先行してしまい、紙媒体の時は「これは大変そうだからもっと目的を絞ろう」とかそういうブレーキが一切利かなくなります。そして最終的にデータマネジメント担当(DM)が、データを収集する側とデータを解析する側とで板挟みになり、悲しい思いをする…どこかで聞いたことあるという方は結構多いのではないでしょうか?
*この作品はフィクションかも知れません。実在の人物や団体などとは関係ないかも知れません。
漠然と研究をやりたいという気持ちが先行してしまう
大規模な臨床研究は、誰もがわくわくするものです。開始前から、目標症例数を見て、出来たら凄いぞ。いや、きっと出来る。そんな希望をもって挑むことでしょう。研究で「最も見たいところ」ははっきりとしていて、それに向けて何をしなければいけないのか、という漠然としたイメージはある。経験豊富な臨床医もたくさん揃っているので、研究グループの総知識量としては凄いものがある。イケイケな心地良いムードになっている中で、プロトコルの中身を少しずつ形にしていこうと、メールでのやりとりや、ミーティングが行われる。
最初から計画が綿密に練られていたわけではない。だが少なくとも、やりたいことがある程度絞られていて、「そもそも論」が少し弱いな~というところを我慢すれば、なかなか筋の通った計画ではあった。だが、ミーティングを重ねていく内に、「これを見るならあれも見なきゃ意味ない」という最もらしい意見が相次いだ。あがってきた貴重な意見に優劣を付けることも何だか気分が悪いし、「もう、オール採用で良いや!」となる。そして気付いたら…
企業治験顔負けの量のCRF枚数になる
DMは、この時点で、このまま進むと悲しい思いをする、という漠然とした不安にかられます。本来であればDMがこの時点で研究者を制止すべきです…が、これは理想的な話であって、一般的にDMにそこまでの力はありません。というより、おそらくDMも、自分の漠然とした不安をしっかりと根拠づけることが難しい…よって研究グループ全体としては「ビクビクしてばかりじゃ何も進まないよ!」と言う意見に落ち着く。そして、設計図から見て沈むことがほぼ確定している船の建造を、DMはコツコツと続けていくしかない状態に陥ります。
いざ研究を開始してみると、採用した項目の多くが、一部の施設でのみ収集が可能ということが判明する。EDCから飛び出る大量の入力画面を前に、各施設のコーディネーターや事務局スタッフのモチベーションも日に日に下がっていく。モニターの苦労の甲斐虚しく、入力欄が綺麗に埋まるはずもなく、虫食い状態のスカスカなデータセットが出来上がる。生物統計の先生には、解析をする価値もないと突っぱねられる…悲惨です。
どうしてこうなった
何も臨床研究に限った話ではないと思いますが、上記はある時点で何らかのテスト・検証を挟んでいない(検証する時間がなかった)というところが大きいと感じます。ダミーデータでも良いので、多施設でパイロット試験だけでも組んでいれば、大河ドラマ級のCRFに無理があったことが早期に判明した可能性もあります。また、なにより関係者全員に、EDC操作マニュアルやデータ入力チュートリアルだけでは習得できないスキルを身に付ける機会も作れます。とはいえ、「サービスイン死守」という周りの空気に抗うのは、なかなか勇気のいるものだとも思います。
また、開始後にダメだと判明したものがあれば、あっさりと飽きらめて切り捨てる、という勇気も必要かも知れません。今までの苦労が勿体ない、と思うのは凄く自然ですが、鑑賞開始10分でつまらないと判明した映画を、チケット代がもったいないとして最後まで見るか、残りの時間を他のものに費やすか、と同じ話だと思われます。身近に経験したものに、研究開始後しばらくしてからバッサリと項目数を切り捨てたケースを経験したことがありますが、英断だったと思います。

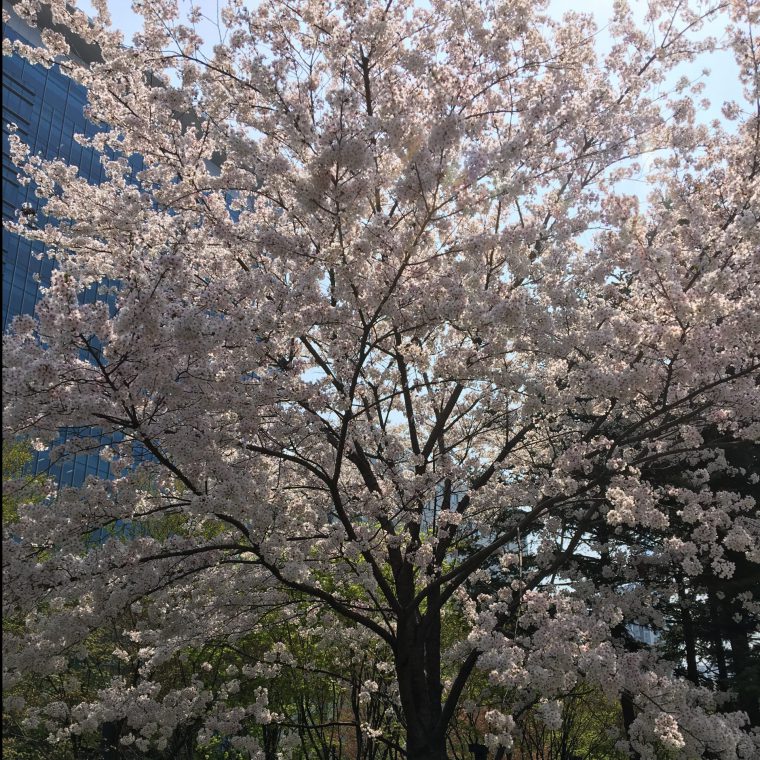






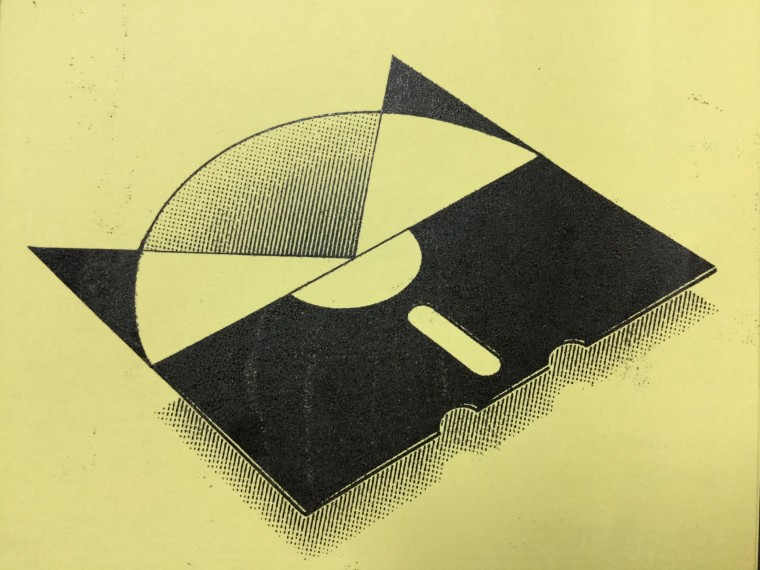
コメント