有栖川宮記念公園にてEHRガイダンス案を考える

ついこの間、米国食品医薬品局(FDA)が「Use of Electronic Health Record Data in Clinical Investigations」というガイダンスの案を公表しました。いわゆる電子カルテ(EHR)の臨床試験における利用についてです。本文中にも書かれておりますが、本来、EHRはFDAの規制対象にはなっていません。そして今回も、EHRの「21 CFR part 11」準拠については論じないと前置きしています。とは言っても、原データとして取り扱うのであれば準拠しないわけにはいかず、FDAも「特定の試験のためだけにEHRに入力されたデータはPart 11の規制対象内」というスタンス。じゃ、もともとあった場合は準拠していなくて良いのだろうか、と未だにこの一言の真意が理解できずにおります。保健福祉省との喧嘩を避けるために、入れざるを得ないだけなのか、どなたかレギュレーションに詳しい方、是非教えてください。さてさて読んでみて感じたことは大きく:EHRを(EDCに)もっと活用しよう、ということと、活用するにあたって同意説明をしっかり考えよう、の二つです。
当然、EDCに必要なデータで、EHRの中に既に存在するものは、そちらから吸い取るのが理にかなっており、否定する人は少ないのかと思います。突き詰めていくと、患者が治験に参加している場合でも、病院スタッフはEHRだけで簡潔してしまうのが理想でしょう。現状では、電子カルテたるものにEDCにある様な高度なカスタマイザビリティーを期待することはできません。EDCにおけるエディットチェックやオートクエリは、構築する側の比較的少ない労力で、原資料の直接閲覧と同じレベルのエラー検出率をたたき出せるというデータもありますが、EHRにこれらを組み込むのは厳しい。となると、EHRからEDCに吸い上げ、EDCでエディットチェック結果を見て、明らかな間違いが判明したらEHRのデータを修正して再度吸い上げ…あれれ、なんだかややこしい話になってしまいます。
そして同意説明。今回読んでいて「あ、そうか」と思ったのが、EHRを使うと決めた場合にそのリスクを患者にも理解してもらう必要があると言うことです。依頼者であったり、CROであったり、もちろん監査するのだからFDA自身も、誰がどの様な形で患者のEHRへのアクセスを許可されるのか、それに伴って、あるいはそれとは別に、情報漏洩のリスクは増大するのか。加えて、同意撤回した場合患者のプライバシーは適切に守られるのか、という問題もあります。
病院で集めたデータはあくまで病院に帰属させて、承認申請に必要なものだけ吸い上げる。目指したいような、大変なような。EHRについても勉強不足なのでなかなか難しい材料ですが、色々考えさせられました。さてさて、eSource Data利用に関するガイダンスの時は業界側から意見が大量に出たのですが、今回は果たして…


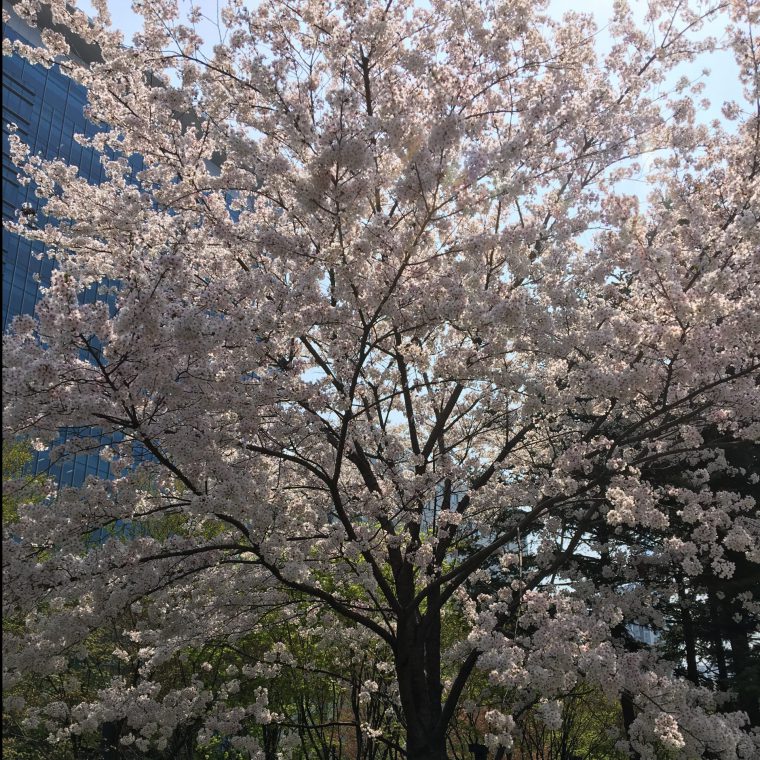



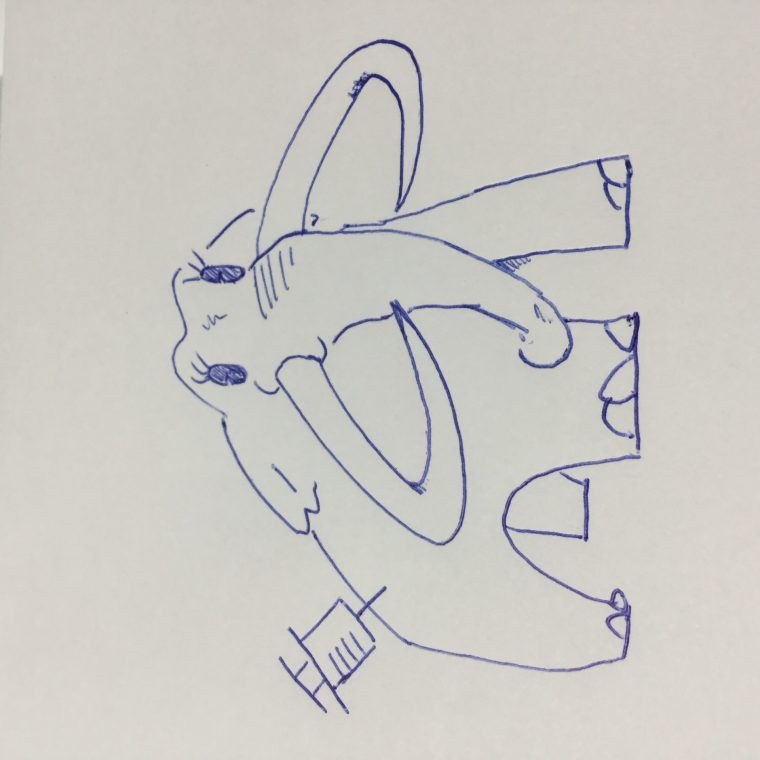


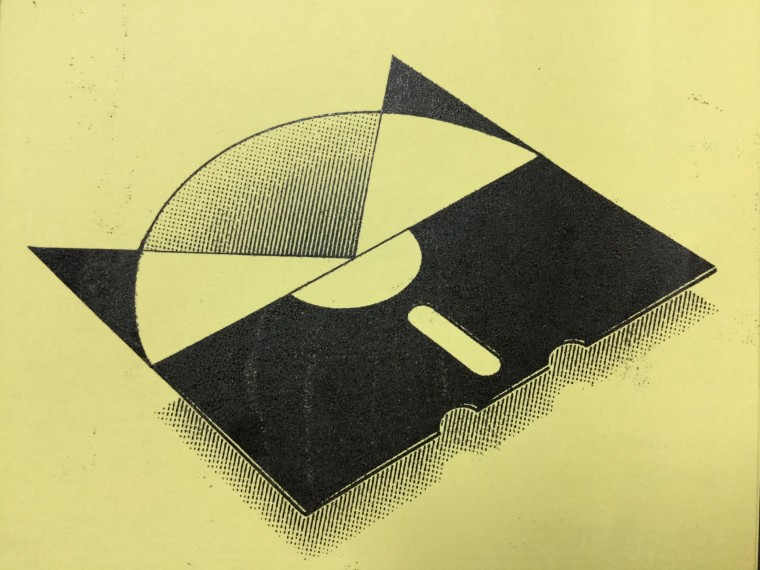
コメント