Erasmus大学病院治験契約奮闘記

オランダ、ロッテルダムのErasmus大学病院にて、とある季節性の病を対象にした治験において、施設選定から契約までの流れを紹介してもらいました。季節性ということで、12月にはがっつりと患者エントリーを開始する必要があり、契約があまり遅れると患者のエントリー自体が絶望的なため、急ぐ必要がありました。スポンサー企業の最初の打診が6月だったのですが、8月末に漸く選定が決まったため、そこからの慌ただしいプロセスが語られました。
基本契約
オランダでは、大学病院連合(The Netherlands Federation of University Medical Centres;NFU)と、オランダ製薬工業協会(Nefarma)が共同で作成した、治験契約のひな形(CTAテンプレート)があります。テンプレートを活用することで契約プロセスをスムーズにすることを目的としているのですが、メーカーや病院側が条項を追加・変更することはしばしば行われるとのことです。今回は、諸事情によりErasmus大学病院の弁護士が色々変更を要求していたとのことで、契約がなかなか締結できずに…
スポンサー予算案VS施設予算案
契約を詰めている間に、試験の予算が立てられました。海外では治験契約はスポンサーと病院長の間では無く、スポンサーと科の間で直接行われることが多いですが、オランダも例外ではありません。また、ポイント表に沿って被験者単価が自動的に決まってくるわけでは無く、各試験で担当CRCが薬局、ラボ、ウイルス、呼吸器のそれぞれに、試験を実施するにあたっての見積もりを依頼します。もちろん、いままでの経験から、担当者側でもおおよその予算立ては可能ですが、スポンサーへの提示はこれらの部署からの返事を以て行われます。スポンサーからも、予算の目安(希望する被験者単価)が提示されますが、今回の例では結果的にスポンサー案より1.5倍高い被験者単価で提示することになりました。
説明文書の翻訳
最終的にスポンサー側と病院側の弁護士がそれぞれフェイストゥーフェイスで話し合いを行い、双方が満足できる形の治験契約ができあがりました。予算の承認と契約案を以ていざ倫理員会へ申請というところで、トラブルが判明。スポンサーが準備している患者説明文書が英文であったため、これをオランダ語へ翻訳する必要がありました。さすがにオランダと言えど、患者説明は自国の言葉で行われます。上がってきた訳文が分かりづらくて、とても一般の患者に問題なく理解できるというものではない。ただ、これ以上遅らせてしまうと、患者エントリーが不可になってしまう。加えて、審議枠が限られているため、試験数が多い場合は先着順になる。ちょっと高いけど外部(商用?)IRBも利用可能ではある。今回は、これ以上遅れてしまうと、患者エントリーに支障が出てしまうため、泣く泣く現状の説明文書訳文で倫理審査委員会に提出することになりました。
今後は、倫理委員会の承認を経て、患者エントリーが行われることと思われますが、特に予算について院内およびスポンサーとのやりとり・交渉が行われるところは大変興味深いと感じました。


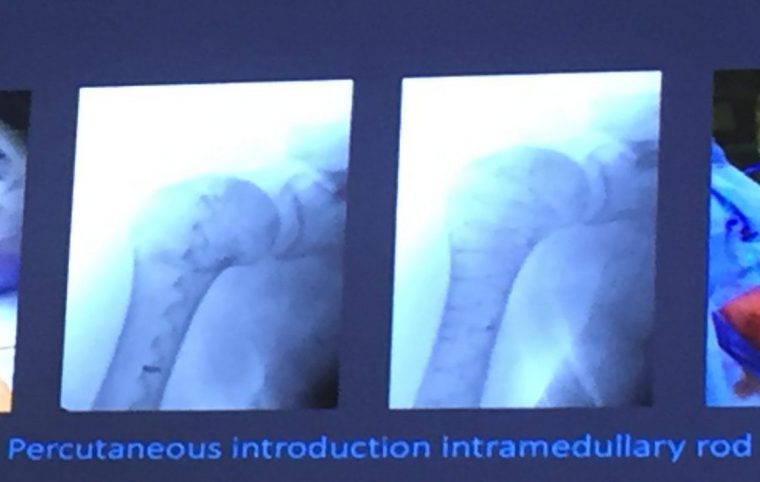






コメント