2001/20/ECを振り返る

先日、CJUG(CDISC Japan User Group)にて、OmniComm Systems, IncのWolf Ondracekより欧州(&オランダ)の薬事規制について講演がありました。以前別の投稿で紹介させて頂きましたが、欧州の薬事規制が2018年の10月からガラッと変わります(Clinical Trial Regulation; CTR)。講演の作成にあたり、CCMOの事務局の方にインタビューも行っており、「ぶっちゃけた」声も聞けて大変有意義でした(CCMOについてはこちらを参照ください)。世の中、思い通りに事が運ぶという保証は無く、合理性を追求してルールを設定しても諸事情により思い通りに行かないことはしばしばありますが、そういう声を聞くことが出来て変な安心感がありました。以下は発表内容とは異なりますが、CTRの前身にあたる現行制度について自分なりに再整理したことを綴ります。
ハーモナイズを目指して…
今から遡ること十数年、欧州ではEuropean Union Clinical Trial Directive(EUCTD; 2001/20/EC)が公開されました。欧州各国は、2004年5月までに施行を義務づけられましたが、オランダは実は2年遅れで対応しています。この遅れには、「合理の面で納得できないものは嫌だ!」という国民性の問題もあったのでしょうが、当初のオランダは人口当たりの臨床試験届出数が欧州内で抜きん出ていました。そのぶん、EUCTDの施行には慎重にならざるを得なかったことも関係していたと思われます。
EUCTDのそもそもの目的は、欧州内での手続きのハーモナイズであったのですが、これに対する反発は少なくありませんでした。個々の試験における被験者・患者へのリスクの度合いを鑑みず、そしてスポンサーが付いていようがなかろうが、全ての試験を同じ(煩雑な)プロセスで管理しようということには無理がある、という懸念の声が少なくなかった様です。実際、施行前後ではイギリスにおける非スポンサー試験(日本で言うところの医師主導治験や臨床研究)の実施(新規届出)はガクンと減り、第Ⅰ相試験の届け出が新たに義務づけられたにもかかわらず、試験届出の総数は大きく減りました。
オランダにおけるEUCTDの施行
同指令では、試験の審査を2段階で行うことが定められました。すなわち、全ての試験において、倫理審査委員会と当局の両方が試験の実施を承認しなければならない、というものです。これを受けて、多くのEU国では当局側で試験の科学的妥当性や安全性を審査、そして倫理審査委員会ではプロトコルと同意説明プロセスの審査をそれぞれ行うことになりました。役割分担をしっかりと行っても、ある程度の重複は避けられず、それぞれが負担する業務量のコントロールも難しくなります。オランダでは、当局の業務内容は倫理審査委員会における実施が不可能なもののみに限定しています。具体的には、全ての試験薬において、EUの安全性データベースの照会(そして適宜審査委員会への情報共有)と、一部の特殊な試験の審査のみです:
プロトコルも、試験薬概要書も、インフォームドコンセントも全て一箇所で審査されます(詳しくはKenter 【2009】, J Acad Ethics参照)。慎重にことを進めたこともあってか、オランダにおけるインパクトは緩やかだった様です。ドイツやフランスでは報告のあったEUCTD施行直前の「滑り込み届け出」等もオランダではなく、届出数は安定していました。一つの委員会が責任をもって試験の実施の可否判断をするため、イギリスで報告された様なたらい回し(Stewart【2008】, BMJ)も起こり得ません。
EUCTRで何が変わるのか?
…の細かい話はまた改めて寄稿したいです。
当初2016年の施行を目指していたEUCTRがそもそも「延期」になったのは、どうもEUポータルとEUデータベースなるものの整備が遅れているため、だそうです。こちらは12月2017年までには活動開始が出来るように現在奮闘中、EUCTR自体は、当該データベースが問題なく活動していることが独立機関の調査により明らかにされた時点から6ヶ月…という風になっております(少し余裕をもって、2018年10月に設定されているのでしょうか?)。そこからさらに3年間の移行期間を設け、移行期間満了後は全ての試験がEUCTRの対象になります。
審査プロセスに関しては、以前の投稿でもざっくりと紹介したとおりですが、興味深いのが「Low-intervention Trial」という新しいカテゴリで、既承認薬を用いた低介入試験を指すものです。この試験については、同意プロセスの簡略化や補償の義務化の緩和等があるとのことですが、「低介入」の線引きは各実施国に委ねられるのか、具体的な事例が示されるのかが今後注目したいところです(尚、観察研究は完全にEUCTRの対象外となります)。日本での同様の枠組みの参考にもなりそうです。



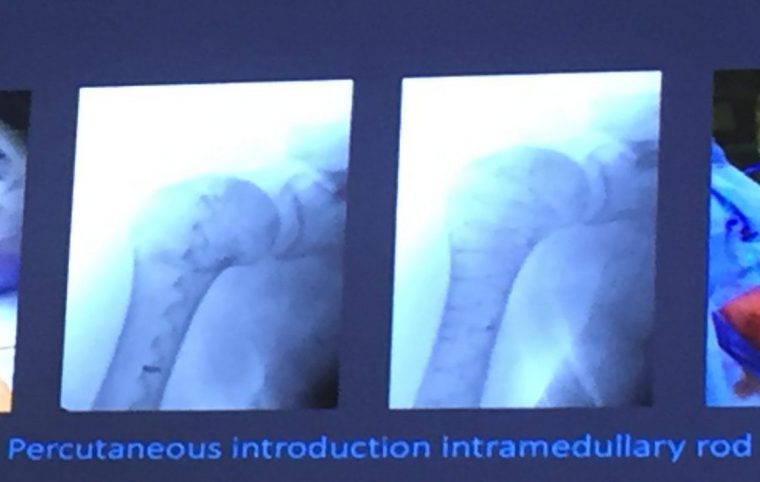






コメント