「敵意はない」と伝えることの難しさ

久々に、どっぷりと通訳の仕事をする機会がありました。やはり、定期的に行っていないと錆び付いてしまうもので、一部大変辿々しい日本語になっていたなと反省しています。今回は色々とチャレンジングなことがありました。その中でも、表現の違い(俗に言う文化の違い)というのは、ややこしいです。行き着く先、目指していることは、お互いが納得できる着地点。とはいえ、双方にそれぞれの立場における「不可抗力」もあるので、妥協が必至な点はある程度事前にわかるというものです。今回は、その「妥協」を前提にした英語の説明を、「妥協」への理解をお願いする日本語への説明に変換する、というものが多かったです。
以前にも触れましたが、同じ交渉の場でも、文化によって表現方法は様々です。真っ正面からぶつかって来なければ誠意が伝わらない場合もあれば、相手の立場に立って提案をした方が好まれる場合もあります。当然、同じ日本(人)の中でも表現に個人差があるように、外国(人)についても同様です。直球で仕掛けてくるフィンランド人も居れば、物腰の柔らかいフランス人も、社交辞令が下手なアメリカ人も居ます。英語が第一言語であるかそうでないかという違いも勿論あります(オブラートに包む、というのはそれなりに語学力を必要とすると思います)。
今回、大きく収穫があったと感じたことは二つ。一つに、敵意が無いということ、無礼のつもりは無いということが相手に伝わることの大切さ。これが明確にできるのと、曖昧に流すのとでは、その場の空気が大きく変わる。会話がぎくしゃくするなどのことでは無く、意見交換であったりブレーンストーミングであったりの成果に大きく影響するものだと感じます。相手が嫌なやつだと感じてしまうと、提案も対案も出しづらくなるのではないでしょうか。もう一つに、通訳する人の理解度の問題。通訳を立てて会話をする場合、それぞれに通訳者が居ることが理想です。しかし現実には、一人の通訳者が、立場の異なるものの間で「板挟み」になります。両者の希望と主張を理解して、混合しないことが重要だと思います。疲れてくると、安易な着地点に誘導したくなる衝動にかられます。それを抑えるのにも、やはり両者の主張の理解が最重要です。






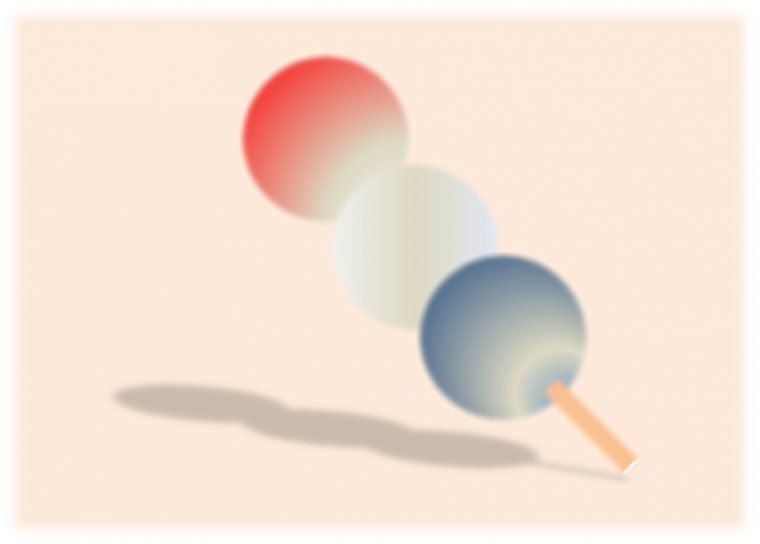

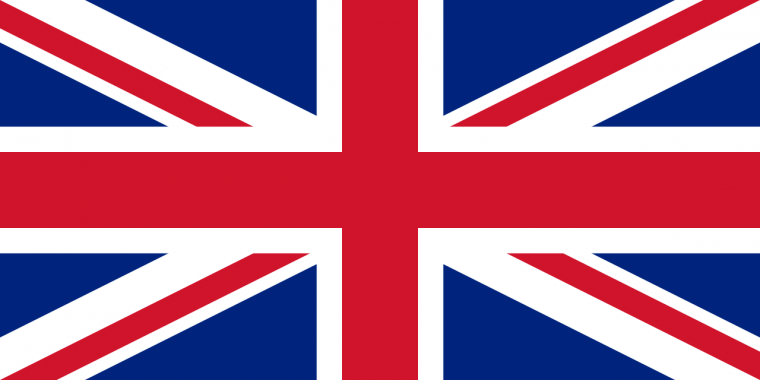
コメント