たぶん失望する英語力

暑くなってきました。最近ずっと敬遠していた日本語小説を少しずつ読むようになりました。きっかけは語彙不足を感じたから。周りに「英語出来るようになりたいなら読書は避けて通れないよ!」と偉そうなことを言っている自分も、実は読書が得意ではなく、重度の遅読家なのです。そんなのでよく大学に出られたねと思うかも知れませんが、読むのが遅いだけで、読んだものはしっかり吸収するので、学習する上で多少の不便は感じつつも、致命的ではなかったです。でもやっぱり語彙力は欲しい…なぜなら、日本語はピンポイントで何かを表現する言葉が大変豊富かつ日常的に使われているから、と感じるから。「凄い」や「微妙」等の言葉が、本来の意味から逸脱して万能な言葉になるなどの個人的には残念な動きもあるが…<dassen>特に微妙においては「なんでこんな漢字なのだろう?」と立ち止まってみると今の使い方がおかしいことに気付きそうなのに。</dassen>
I think maybe he will sign the contract
前置きが長くなりましたが、今回は日本でよく見かける「誤解されているかわいそうな英単語」を2つピックアップしてみたいと思います。「正しい使い方を~!」と啓発の意味も込めていますが、前置きにある「語彙」がどれだけ重要かというところが一番のポイントです。一つ目は、「maybe」について。この単語は、日本語の「多分」の英訳として多用されます。見出しにある英文も「多分契約に署名してくれそう」というのを英語で伝えたかった(それなりに英語が出来る)方の言葉です。でもこの英文のままでは、聞いている側は「あ、契約取れるか自信が無いのかな…」という意味で受け取ります。「maybe」は「多分」の訳として必ずしも間違いではないでしょうけれど、一般的には「7~8割方イケる!」と言うニュアンスで使う「多分」の英訳としてはふさわしくありません。
「多分」という言葉は幅広いニュアンスで使われますが「イケるかも知れないよ…多分…」と「多分大丈夫じゃないか?」では、「maybe」と訳して大丈夫なのは前者のみ。でも正直、その場合でも「I might be successful」などの言い回しの方が自然かなとも思います。「maybe」の間違った使われ方が蔓延しているので、スマートニュースのCMで吉岡里帆が最後の「oh, maybe!」で何を言いたいのかも、よくわからないです。
期待通りでなくて失望した
二つ目は、報道などでたびたびみかける、「disappointed」を「失望した」と訳す傾向について。失望って、かなり厳しい批判のように受け止められますが、「disappointed」自体は「期待していたのと違う」ということで、状況次第で「残念」「がっかり」「遺憾」「失望」のいずれにも成り得るかと思います。一律「失望」と訳するのは、煽りたいというマスコミの性も関係しているのかも知れませんが、報道の翻訳を鵜呑みにすると事実と全く異なる印象を受けてしまう良い例です。
近年少しずつ改善されているような気はしますが、日本の報道はいまだに外国語で行われた発言を全て日本語で吹き替えてしまう傾向が強いです。あるいは適当に切り貼りして、英語で発言している内容と日本語の字幕が一致していない場合もあります。報道される発言が過激だと感じたらネットで原文を見てみたら実は大したことなかった、なんてこともしばしば。「disappointed」の例では、声明文の締めにきちんと今後の希望・展望に関する言葉が述べられていたりしますし。
脱・単語カード
今回の例はいずれも単語カードの様に1つの日本語に対して1つの英語があるという認識から生まれる誤用だと思います。単語の集まりが国語とイコールではないし、各単語の文節における使い方も含めて「語彙」なわけだと思います。なので語彙力を高めるにはやはり読書しかないのかなと思います。もちろん、NETFLIXで洋画を字幕で鑑賞するのもお勧めです。
ついでに最近読んだ本で面白かったものを2つ紹介します:
半沢直樹風の「リストラ日和」は、人間関係の描写が凄く丁寧でなかなか楽しめました。
[amazonjs asin=”4758439214″ locale=”JP” title=”リストラ日和 (ハルキ文庫)”]
サイコパスに振り回される学生を描いた「死刑にいたる病」は、読んだ直後に「ポカン」となります。で、直後にじわじわと「あ、だから怖いんだな…」となります。多分。メイビー。
[amazonjs asin=”4150313008″ locale=”JP” title=”死刑にいたる病 (ハヤカワ文庫JA)”]





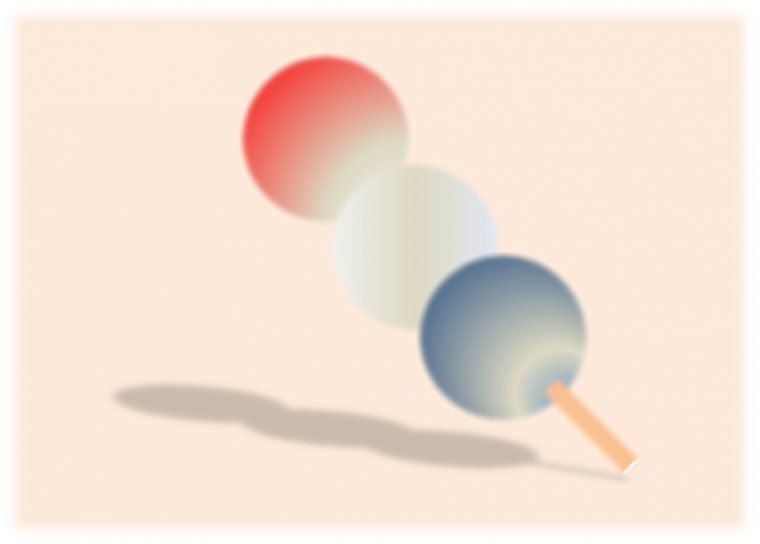


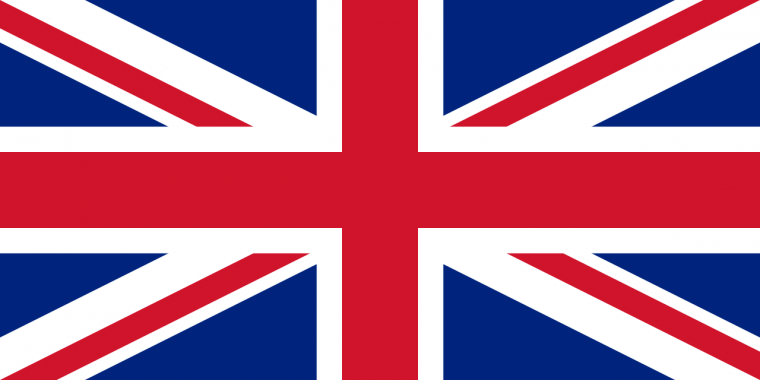
コメント