期待しないスタイル

通訳のお仕事の話です。とある出来事があまりにもショッキングで、まさに「一生の不覚」以外に言葉が思い浮かびませんでした。しかし、最初の困惑が過ぎてみて、少し落ち着いて振り返ってみると、やはり「いいことは おかげさま わるいことは 身から出たさび」だと感じました。やるべきことに集中する。通訳においては特に重要なことだと痛感しました。エピソードの詳細は、この件が「時効」になるまでちょっと書くのを躊躇ってしまいますので、フワフワした話になりますがご了承下さい。
日本語を話す人と英語を話す人の間に入って、一人で通訳をしばらくしていると、人間の心理としてどちらの言い分にも引っ張られ、板挟みの状態になります。重要な会議では必ず日本語圏、英語圏の双方に通訳が付くのが定石なのは、このためなのだと、日々のお仕事で実感しています。双方の意見・認識・期待に食い違いが生じると、頭の中が大変忙しいことになります。今はAさんの立場、次はBさんの立場、と言うように切り替えていかなければなりません。一つの会議を丸々このスタイルでやると、集中力がいくらあっても足りませんので、常にこうするわけにはいかず、ある程度は「仲介屋」の立場を取ります。英語を日本語に通訳する前に、例えば返って来るであろうと想定する質問への答えを先に英語圏から導き出して、通訳者の理解も深めた状態ではじめて和訳をする(逆も然り)。表現の違いによる誤解や衝突を避けるには、こういったこともある程度は必要だと思います。
危険なのは、これをしばらくやっていると、通訳しているもの自身が、英語圏と日本語圏、両者の間にお互いの立場への理解が芽生えはじめていると錯覚してしまうことです。どこかで、「もうこれだけ腹を割って話しているのだから、そろそろ解ってきてるよね」と英語圏・日本語圏のどちらかあるいは双方に期待をしてしまいます。どこからどこまでが社交辞令なのか、読み取れなくなります。
そして、丸く収まったと思ってしばらくノーマークでいると、約束していたはずの事と、全く異なることが起こる。何が起きているのか、一瞬理解できなくなります。でもよくよく考えると、「きっと大丈夫だよね、やってくれるよね」と曖昧に流してしまった些細なことが数カ所あり、そこから多段ヒットして致命傷…さらに言うと、この多段ヒットを許した根本の原因は、最後の話し合いの冒頭で英語圏側の日本語県側に向けた社交辞令をそれとして見抜けなかったことにありました。
と言うことで、今回のポイント:
- 通訳者として、「通訳している自分」と「仲介している自分」をきっちり分ける
- 相手が理解していると勝手に錯覚していないか、常に自問自答する
- 通訳されるどちらかが、相手方に間違った期待を抱いていないか、注意する
しつこく確認すれば良かったのだろうか?と、そういう訳でも無いと思います。会議になりませんから…ここの案配については今後の研究課題です。






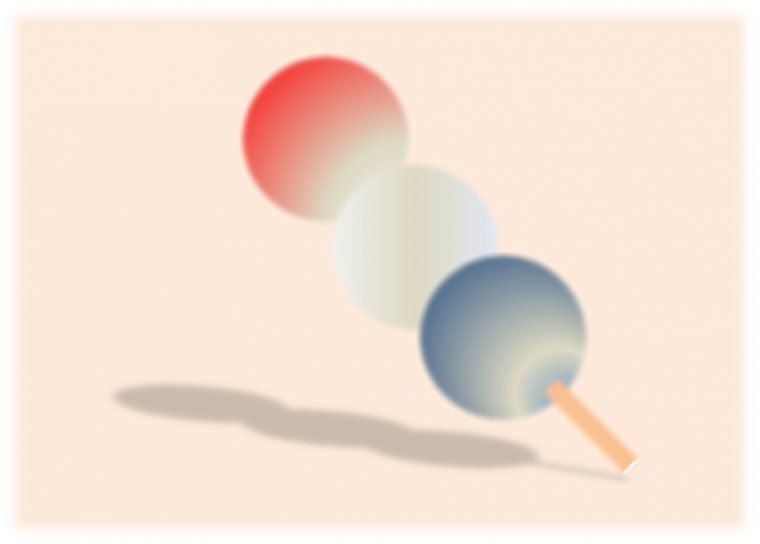

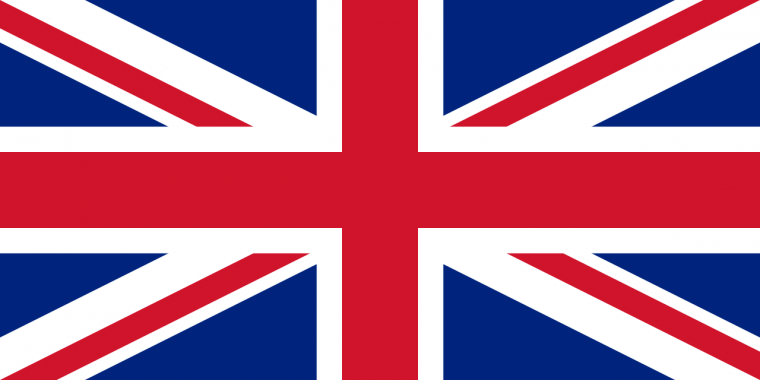
コメント