オランダ人は三色団子の夢を見るのか?
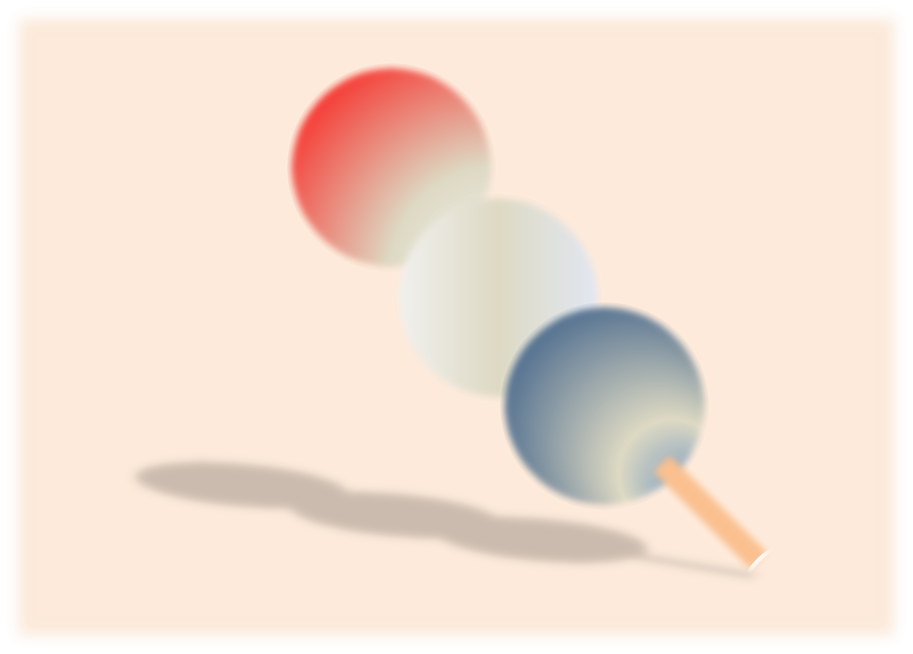
夢は何語で見るの?考えるときは何語なの?等という質問をたまにされます。正直、よくわからないのです。夢の記憶は後付け(目覚めの瞬間とも)と言う話もありますし、ぶっちゃけ言いますと夢の内容自体、私の場合起床後5分以内に綺麗さっぱり記憶から抹消されます。考える言語は…後述します。大概、こういった質問は飲みの席で受けることが多いのですが、こんな顔なのにダイの大冒険の素晴らしさを熱弁してしまうため、「おかしい。何かがおかしい。」と皆さん気にかけてくれることが多いのです。そして、質問を受けてから「そうだね…」と言い、一瞬目が遠くを見てしまうことがあります。質問が嫌とかではなくて、色々思い出してしまうので。
物心ついたときから、私はオランダ語と日本語の両方を理解していました。いや、正確には、片方の言語が理解できなかった自分を思い出せない、という事でしょうか。自宅の屋根裏部屋で開校された日本語幼児教室、車で送り迎えの記憶があったオランダの幼稚園…どちらも鮮明に記憶に残っており、どちらでも言葉の面で不自由をした覚えはありません(両親の工夫と苦労は絶えなかったとは思いますが)。オランダ版セサミストリートを見つつ、母側の親戚や友人から送られてきたビデオ(ベータマックス)で日本の番組もある程度見ていた、と言うのが大きかったのでしょう。
日本語期
いつまでかははっきり覚えていませんが、あるときから兄弟の会話がほぼ日本語オンリーになっていました。後から解ったことなのですが、これはを同時性バイリンガリズム(注:出生から二つの言語を学ぶタイプ)にはよく起こる現象らしいです:子供はどちらか一方の言語を「第一言語」と位置づけて、日常的な会話はその第一言語で行うようになるそうです。母国語と言う言葉がありますが、私にとっては母国の語、ではなく母の国語を意味していました。毎週土曜日に日本語補習校と言うものに通い、そこで知り合った日本人コミュニティの友達と遊ぶことが多かったのもあり、しばらくは日本語がメインになっていたような気がします。
尚、「バイリンガルってやっぱり学習上は不利とする研究結果を読んだことがある」という話を聞くこともありますが、こういう研究は中身を見ていくと貧困や居住地域等の交絡因子を完全に野放しにしているものが多いです(結論ありきの研究と疑われているものもあります)。小学生の間は多少学習の遅れという傾向はあったにしても、中学校に入るまでには差は検出できなくなっています。
オランダ語期・英語期
次第に、オランダ語の方が日常会話を占める割合が多くなります。前述の日本語補習校は小学校までしか通っていない、ということも関係していたかも知れません。テレビ番組は、イギリスやアメリカからの輸入品を字幕付きで放送していることが多かったため、このあたりから英語が自然と身につくようになります。友達付き合いも多くなり、趣味で英語の読み物に触れる機会も多くなるため、多分思考も全てオランダ語・英語になっていたと思います。大学では、教材の半分以上が英語であり、論文の類いはほぼ100%英語でした。
そして社会人…結局何語で考えるのか
はっきりと断言出来ませんが、おそらく、考える際の言語は特にない…と思います。何かを文章にしなければいけないときは、もちろんその言葉で考えますが、今回の雑文の様に、書き物が日本語であれば頭の中も日本語ですし、そうでいない場合は別の言語です。誰かと会話をしなければいけないときも然りで、例えば日本人と会話をしていれば、ブローカ野もウェルニッケ野も日本語モードです。日本人を目の前にして、英語だとかオランダ語を話すのが、実は一番難しいと感じています。「ねーねー、オランダ語で【三色団子買ってきて】ってなんて言うの?」とか聞かれると脳が冗談抜きで一瞬フリーズします。
さて、考える際の言語は特にないと言っておきながら、ここで一つ面白い現象があります。私は大学で医学部バイオメディカルサイエンス科というところで勉強をしていたのですが、こちらの学科は、「考えること」に凄く重きを置いていました。試験の内容も、限られた情報の中から何らかの答えを導き出すものが多く、教科書やシラバスに出てこなかった内容が試験に出てきたことについて文句を言うと、「覚えて解決したいなら医学か薬学行きなよ」と言われたり、「解けないなら、何故解けないと思うかを書きなよ。解かなきゃダメ、とか答えは一つしか無い、とか設問のどこにも書いていないよね?」とバッサリでした。こんな一見理不尽な環境で培われた「考える力」ですが、いざ日本に来てみると…できないのです。いわゆる、日本語で書かれている文章の批判的吟味が全くできない。英語論文を読んで日本語で問題点を指摘することができない。頭の中で英語で理論を組み立てて、そこから日本語に「訳す」という、ワンクッションが必要になります。
外国語を習得するタイミングは、その言葉を使うときの脳の働きに影響するようです。同時性バイリンガル(そしてとりわけ男性)の場合は、どちらの言語も左脳を占拠してしまい、言語をまたいだ理論立てが苦手、ということがあるのかな、と思ったりします(本題からすこし逸れますが、言語で思考回路が変わってしまう現象について同ブログのこちらの記事もおすすめです)。








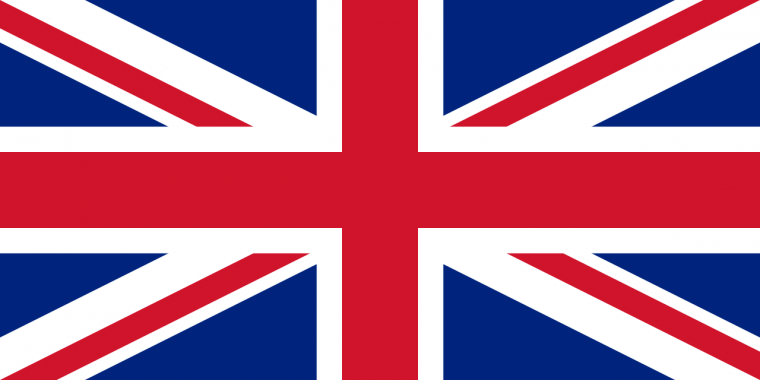
コメント