リスクベースモニタリング?
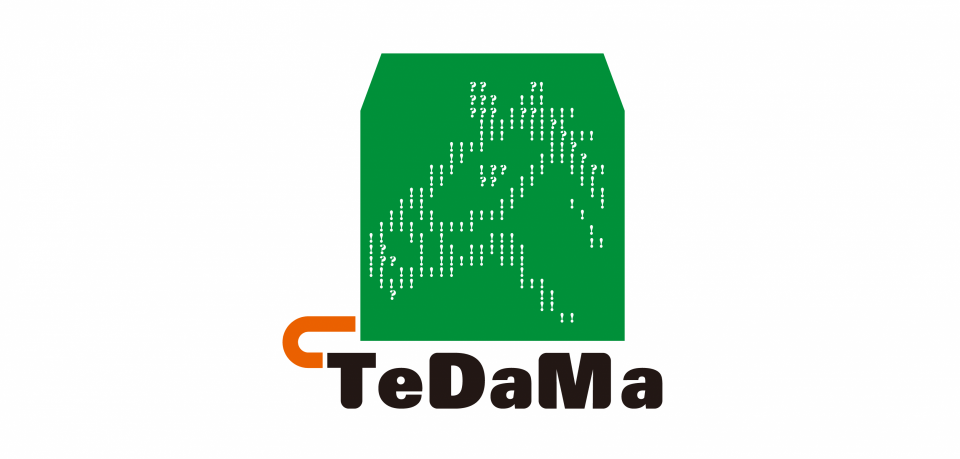
モニタリングは、臨床試験を実施するにあたってなくてはならないものなのです。モニターが何らかの方法で各参加施設の医師・CRCと打ち合わせをしたり、患者エントリーの進捗を確認したり、原資料をSDV(直接閲覧)することでデータの品質を確認したりします。モニター自ら参加施設に足を運ぶことが多いことも関係し、かなりのコストが発生します。試験予算の3割にも達するという推定もあります。製薬企業はじめ、モニタリングのコストをなんとか抑えようと、中央モニタリングであったり、重要な項目以外はランダムで全被験者の一部のみを100%SDVの対象にするであったりと、色々試します。
注意しなければならないのが、SDVだけに焦点を当てたところで、コストカットへの影響は限定的だと言うことです。モニタリング=SDVというイメージが強いですが、実際施設に出向いたモニターは様々なことを確認します:
- プロトコルの遵守状況
- 被験者保護
- 試験薬管理状況
- 被験者エントリー状況
- 原資料と症例報告書(紙であれ電子媒体であれ)の整合性
SDVだけをカットできたところで、施設訪問の必要性はあまり減らないのではないか?と懐疑的になるのは自然です。とは言え、単純にタイムロスで言えば、100%SDVを維持するのにかかる労力は相当なものなのも事実でしょう。その労力に見合った成果が得られているのかについて、興味深いデータがあります。

100%SDVされた1168の臨床試験の全データのうち、何らかの修正があったのは3.7%。そしてSDVによる修正は、全データの1.1%程度です。当然、下流のデータクリーニング時にどのみち拾われる類のものもそこには含まれていると考えるのが自然ですので、実際のSDVの影響度は更に小さい可能性もあります。また、別の研究では、オンサイトで発覚した不一致等の大部分が中央モニタリングでも充分検知できた類のものだと結論付けています。
SDVは不要という話につなげるのは強引ですが、少なくとも100%SDVを続けていくよりもっと合理的な方法があるのでは、ということにはなります。一部のデータがSDVの結果修正されるのは事実ですので、問題はそれがどのデータである傾向が強いのか、あるいはどの施設で間違いが起きやすいのか、に焦点を当てることです。そしてこの考え方が、巷で騒がれているリスクベースモニタリングのアプローチへとつながります。
今回はここまで。結局導入部だけで終わってしまいましたが、次回は具体例をいくつか紹介します(2016年1月5日更新予定)。

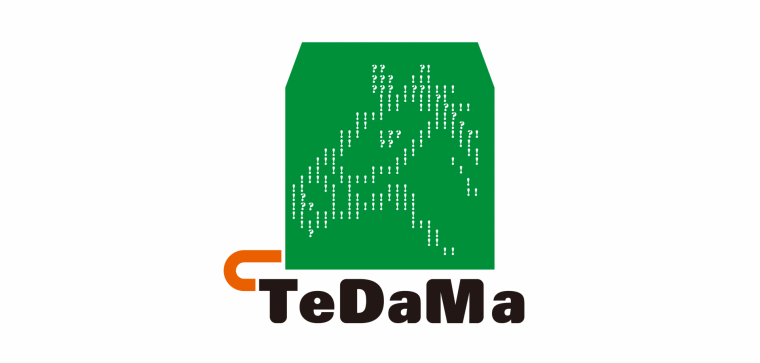
コメント