選択的&動的モニタリング
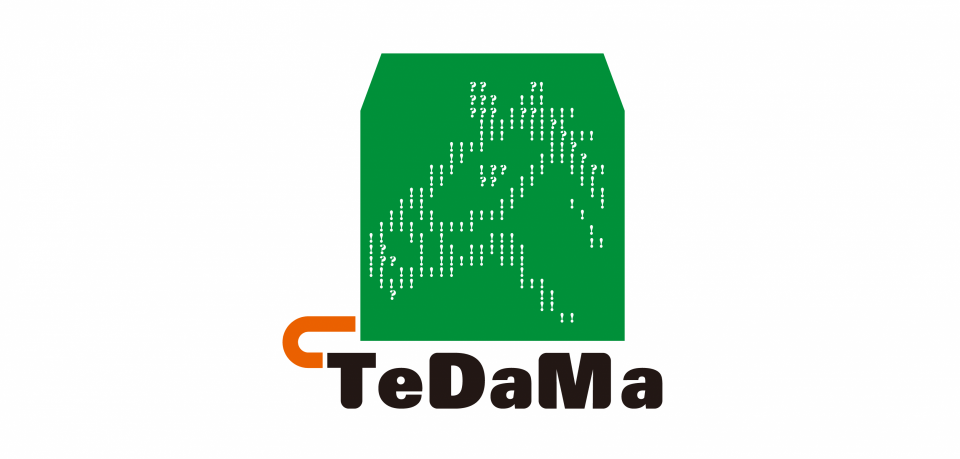
SDVに直接影響されるデータが1%程度と報告している研究を前回紹介しましたが、この1%の中には重篤な有害事象や除外基準や中止基準に関わってくる重要なものも当然含まれています。闇雲に100%SDVを続けていくのは考えものですが、何処を削れば良いのかは悩ましいところです。ただ、この1%が全項目または全施設に均等に分布しているか否かがポイントとなります。例えば、有害事象などは他の項目に比較してSDV時の修正率が高いことが知られています。施設間でも、EDCに対する理解度・熟練度の違いなどがミスにつながる可能性もあります。
選択的モニタリングも一つの手…
従来の100%モニタリングをせずにこれに対応する一つの方法として、選択的なモニタリングがあります。例えば、有害事象のフォームのSDV、ならびに有害事象の報告漏れ(あるいは過剰報告)が無いかの確認は必ず100%行い、それ以外の項目に関しては「抜き打ち」で一部の施設・症例のみを確認します。または、EDC入力トレーニング後の最初の症例のみは100%SDVとし、その結果次第で以後のモニタリングのポリシーを決定するというアプローチも考えられます。この方法では、モニターの現場の拘束時間は削減できるものの、訪問回数自体を削減するのは難しく、「抜き打ち」という言葉からも示唆されるように100%未満SDVをする根拠がはっきりとしないという問題があります。初回は100%SDVをしてから施設別に方針を決定する場合も、後から主担当が多忙などにより治験に割ける時間が半減し、結果一時的にチェック機能が緩むなどのことは充分に起こり得ます。
…でも理想は動的モニタリング
どの施設、担当者、あるいは被験者が「ハイリスク」であるかを、「a priori」決定するだけでは効果は限定的だと考えています。SDVを一部データに絞っても、診療録の準備から担当者のヒアリングの時間調整等による施設側の負担もこれではなかなか軽減されません。また、場合によっては手厚くSDVをしなければならなかったケースを放置してしまうことにもなってしまいます。理想は、モニタリングが必要なケースを何らかの方法で見極めることです。これを見極めるために使用する指標を、Key Risk Indicators(KRI)と呼びます。代表的なものに、有害事象の報告件数とオートクエリの発生率がありますので下で紹介します。あくまで二つの例で、非営利組織のトランスセレレート・バイオファーマ(TransCelerate BioPharma Inc.)がRBM特設ページで公表しているライブラリ(エクセル形式)には、141のKRIが列挙されています。
報告件数の偏りから報告漏れを嗅ぎ付ける
前回も触れましたが、任意にフォームを追加する有害事象等のイベントは、中央モニタリングのみでは「入力漏れ」を検知するのは大変困難です。ですが、有害事象の数についてある程度の「期待値」を設けることや、施設間で被験者毎・ビジット毎の平均報告件数を割り出して比較することは出来ます。報告件数が突出して少ない施設を訪問し、診療録を入念に確認して報告漏れを洗い出すというアプローチです。このアプローチは、一施設当たりの症例数が一定以上であるため、「数をこなす」ことによる施設スタッフの熟練度が期待できる状況で効果的だと考えられます。一方で、日本国内では決して珍しくない「施設当たりの症例数が2、3例」の様なケースでは、過少・過剰報告が多数のため有害事象報告件数が指標として機能しない場合も考えられます。少々余談となりますが、多くの治験依頼者が日本国内でリスクベースモニタリングに踏み切れずにいるのには、こういったことも背景にあるのかと思われます。また、日本の医学教育のカリキュラムで臨床研究というトピックが限定的な扱いのため、施設スタッフの能力が欧米のそれとは異なり、ベースにある臨床研究への理解が低く、過少・過剰報告が起きやすい…という懸念もよく耳にします。
色々見えてくるオートクエリ発生率
さて、昨今のEDCには、エディットチェック・オートクエリ等の「入力担当者に矛盾を指摘し、対応を要求する」何らかの機能が備わっております。これの発生率や発生後の未対応期間などは、SDVの要否以外にも、施設スタッフが入力をスムーズに行えているかの重要な指標になります。例えば、今までそういったことが無かったのに、特定の症例に対してオートクエリが大量に発生している場合は、再度トレーニングを行うことで問題が改善する場合もあります。
これらの「動的なモニタリング」は、費用削減(そして施設のモニタリング対応の負担軽減)として効果が期待できますが、手動ですべてを確認し、SDVの要否をはじめ様々なことを調整していると、下手すると100%SDVの方が相対的に少ない労力で済む…といったことも起こり得ます。リスクベースモニタリングを成功させるにはある程度の自動化は必須と言えるでしょう。次回は、このことについて、リスクベースモニタリングとEDCシステムの関係性を見ていきたいと思います。
また、英語音声のみですが、OmniComm Systems, IncのRBM専門家Steve YoungによるWebinarも是非ご覧下さい:

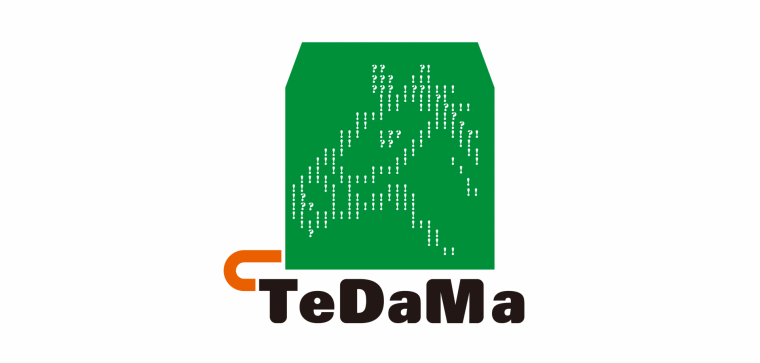
コメント