EDCをストレス無く使ってもらうには

プロトコル、構造定義書、エディットチェック仕様書、そして受け入れテストの計画及び結果報告と、前回の記事で紹介した作業を実施するにあたり何かと書類が発生します。ですが実際には、データベース構築をする時点で、これ以外にも割付計画、解析計画、モニタリング計画、データマネジメント計画等々も明確になっている必要があります。前者二つについては、直接的な関係は無いように思えますが、被験者割付を機能として実装しているEDCもあれば、そうでなくとも何らかの形で割付とEDCは連動させる必要があります。解析についても、臨床研究の実施開始後に、データの集め方が意図している解析に合っていないということが発覚することはしばしばあります。また、それぞれの計画について、「その通りにやりました」ではなく、やった結果をきちんと報告書として残すのも、運用によっては必要になってきます。考えれば考えるほど頭が痛くなりそうです。さて、今回はそういったドライな話はいったん忘れて、現場レベルで必要なことについて綴ってみたいと思います。
ヘルプデスクの設置
自社・自施設で管理するEDCシステムの場合は、当然参加施設からの問い合わせもすべて自分でなんとか捌かなければいけないことになります。EDCのサーバーをEDCベンダーにホスティングしてもらう(サーバーの提供・維持管理下をやってもらうこと)場合は、パスワードの再発行等の簡単な問い合わせはベンダー側のサービスに含まれていることもありますが、それ以外の試験特有の操作については、別途サービス契約を結ぶか、自社・自施設で出来るようにするかしかありません。ヘルプデスクのややこしいところは、少ない時は全く問い合わせが無く、多い時はその場で捌ききれず溜まっていくことです。

また、EDCシステムがウエブベースだからと言って、全ての環境で同じように動作してくれるとは限りません。Google社のChromeでは問題なく動作するものが、Microsoft社のInternet Explorerでは正しく動作しない(逆もしかり)ことは、度々起こります。こういった、インターネットブラウザ間の違い自体は、昨今では標準化が進んでいるため少なくはなってきています。ですが、ユーザー側で様々なアドイン(○○ツールバー等)を自由にインストールできることや、ネットワークの環境が各参加施設で異なるため、全ての事態に備えることは難しいです。難しい問題ですので、こちらについては次回詳しくお話しします。
「ページ」のめくり方
まず、一番に必要なのは、EDCの操作マニュアルです。紙媒体の症例報告書はわざわざ「ページのめくり方」であったり「有害事象ページをバインダーに追加する方法」等をわざわざ記述するまでもありませんが、EDCだと基本がクリック(モバイルEDCならタップ)と文字数時の入力がすべてですので、パラパラめくるのに比べると直感性に劣ります。当然、2歳児がスマホの写真閲覧アプリを問題なく使いこなして一人で悦に入っている時代ですので、次第に必要なくなるかも知れませんが…。現時点では、ログイン・パスワードの変更、データ入力、有害事象フォームの追加、クエリが発行されている場合の操作方法、電子署名、等々わかりやすく操作方法を記述していく必要があります。言葉で説明するより、スクリーンショットを多用した方が短時間でわかりやすいマニュアルが作成できます。
入力マニュアル
紙の症例報告書の時代と比較して、エディットチェックを駆使すること、そもそも入力可能桁数や特定の入力形式の強制等の制御がEDCでは可能であるため、必要性については賛否両論ありますが、作る場合は多いです。こちらは、前述の操作マニュアルとは異なり、どういったときに何を入力するのか、等を記したマニュアルです。EDCのみでは制御しきれない場合等で、別途説明が必要な場合に補足的に使われる場合もあります(全角・半角の自動切り替え等)。操作マニュアルを兼ねて作成される場合もあります。
本当に読んでくれていますか?
苦労して作成するマニュアル類ですが、ヘルプデスクに届く問い合わせの多くは英語のネットスラングで言う「RTFM」系のものです(Read The Fine Manualの略;グローバル化の時代、略語として覚えておいて損は無いのですが大変失礼な言い回しですのでご注意下さい)。マニュアルの内容がわかりづらいのか、単純に読む時間が無いのか、はたまた担当者が変わったばかりで操作に不慣れなだけなのか…理由は様々です。こういった類の問い合わせが大半(問い合わせの9割というのも決して珍しくありません)を占めてしまうと、「作るの大変だし次回からはマニュアル類は省略しようかな…」という気分になってしまいがちです。ただ、マニュアルがあれば、問い合わせに対してマニュアルのページ番号を伝える、あるいはマニュアルの該当ページを抜粋してメールに貼り付ける・添付する等で対応に要する時間が少なくなるので、決して無駄ではないと考えています。問い合わせをしてくる側も、故意にマニュアルを読まないわけではなく、作業が進まなく非常に困っていて、マニュアルを見ればすぐ解決すると言う発想がない場合が大半だと感じています。昨今の電子機器に付いてくる分厚い取り扱い説明書を見れば、マニュアル=面倒くさいという先入観は致し方ないのかなと感じています。
さて、準備が整い、スタートアップミーティングや施設のトレーニングを順次行っていき、いよいよ患者登録・データ入力開始です。次回は、上で少し触れた、施設から上がってくる不具合への対応方法について少し書いてみたいと思います。







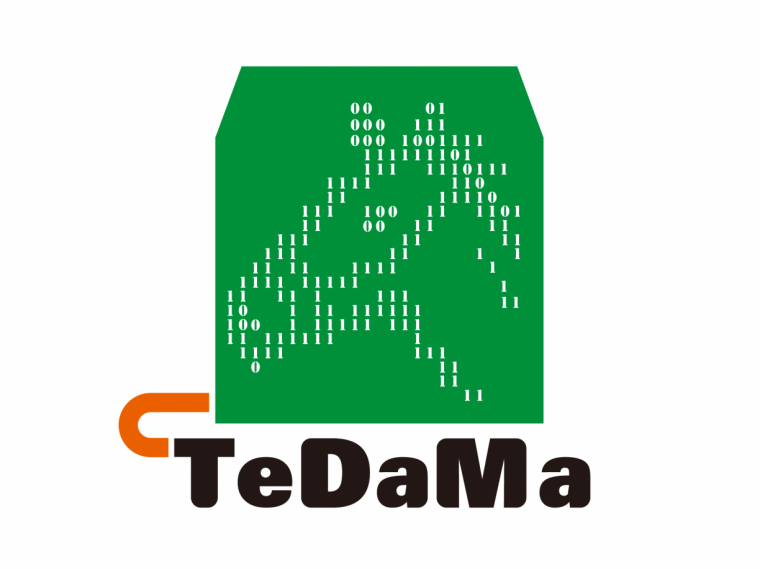

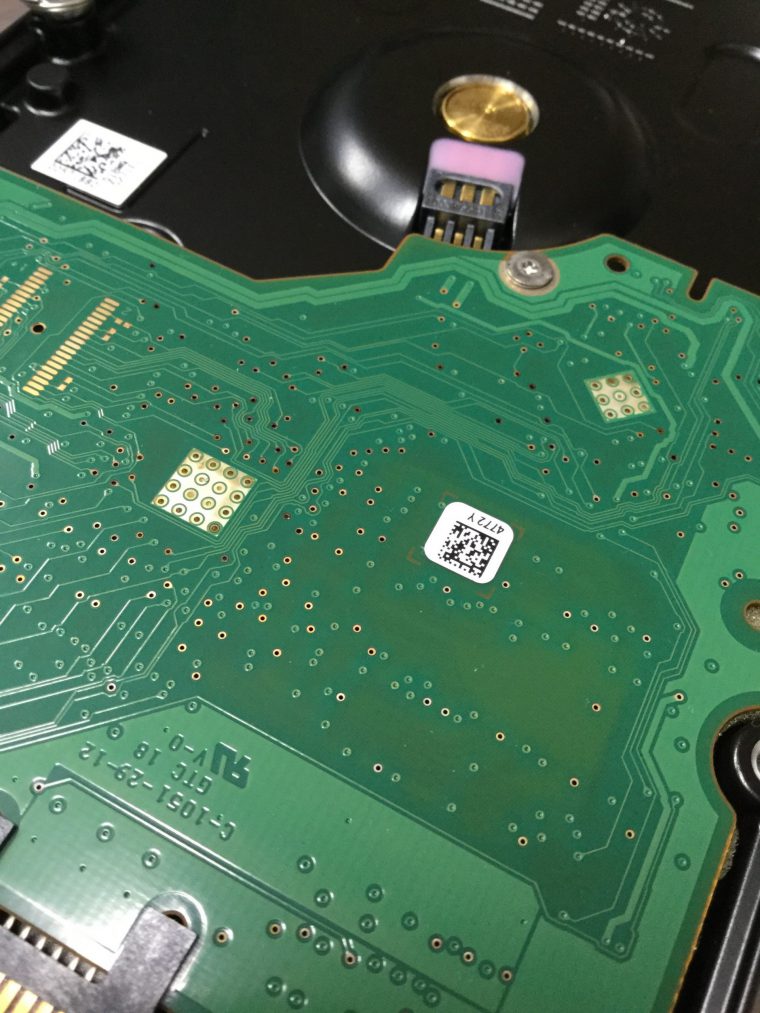
コメント