「出来る」と「やりようはある」の違い【その2】

前回に続き、あれもこれもと豪華な機能が無い場合の工夫の仕方についてです。今回はワークフローに焦点を充てたい思います。文書(コンテンツ)管理システムなんかだと存在意義そのものなのですが、EDCとなると仕様が製品によって大きく異なるものにワークフローというものがあります。あまりピント来ないかも知れないのでイメージ図:
おわかりかと思いますが、ほんのシンプルな一例で、フローは試験によって様々です…何かしらのワークフローが組み込まれているシステムでは、多少のカスタマイズは可能だったりします(が、一般的には現場の運用を合わせた方がコスト面からもスケジュール面からも好ましいと思われます-炎上しがちな話題なのでまた別の機会に)。さて、フローが細かく設定出来ない場合でも、等しく全てのEDCに組み込まれている機能があります。
監査証跡の有効活用
毎度おなじみの監査証跡です。作業記録が事細かく記録されるため、初心者は何かと迷惑がられる機能だったりします。ですが、このブログでもしつこく述べている様に、やっていることが全て、何も考えること無く記録されるのは素晴らしいことです。毎週の業務報告書を作成するにあたって「水曜日何やったか思い出せない…」等の悩み事に、EDCは無縁です。監査証跡を確認すれば、特定の期間でワークフローに反することが行われたのか、ということが完璧に確認出来ます。極端な話、EDCに「データ凍結」以外のワークフローの機能が何一つ無かった場合も、先の図のワークフローの各ステップにおいて「やってはいけないこと」が発生したかどうかは全て確認できます。
基本的なやりかたとしては、特定の試験の変更履歴を定期的に確認することです。日付の範囲を指定して監査証跡を出力すれば、例えばSDV開始時からDMのチェックまでの間にデータに対して何らか変更が行われたかが確認できます。そのときに万が一「不正」が見つかった場合にどうするか、という運用を決めておけば、とりあえずワークフローとしては機能します。
紙ペラと比べると
少し前にアップした「紙ペラを改めて考える」と照らして考えてみます。ワークフロー等を制御する特性・機能は紙ペラ自体に何もありません。ですが、特殊なケースを除いては原本は一つだけ、そして変更を加えるにはその原本を所持していなければいけないという制限がついてきます。モニターに症例報告書を持ってカルテ庫にこもっている間は、(モニターが変な気を起こさない限り)症例報告書の変更は物理的に不可能です。それ以外に、変更が行われてはならない期間があった場合は、症例報告書を鍵付きキャビネットにしまう等すれば良いです。これを電子媒体に置き換えて考えると、例えばアクセス権を特定の人のみに与える、と言うことになります。これを、もう少し自由度を高くしたものが、EDCのワークフロー機能でと考えることもできます。
ですが、そもそも紙媒体においてこういった運用が適当である理由は、変更が行われているかが、書類全てを目視で確認しないとわからないことにあると考えています。ボタン一つで「大丈夫」か「全然大丈夫じゃない!」のどちらかの答えが簡単に出るEDCでは、何もこの考え方に縛られる必要は無いです。むしろ、こんなに簡単に確認できるのだから、こまめに監査証跡を確認する癖をつけても良いのにと思ったりもします。解析担当にデータ出力を頼まれた→該当症例において前回の中間解析から変更が無かったか、監査証跡をチェック、と言うように。
答えは一つでは無い
と…偉そうな見出しで締めますが、工夫で解決するか、お金(&バリデーションにかかる労力!←軽視されがち)でなんとかするか、考える材料(燃料)になればと思います。






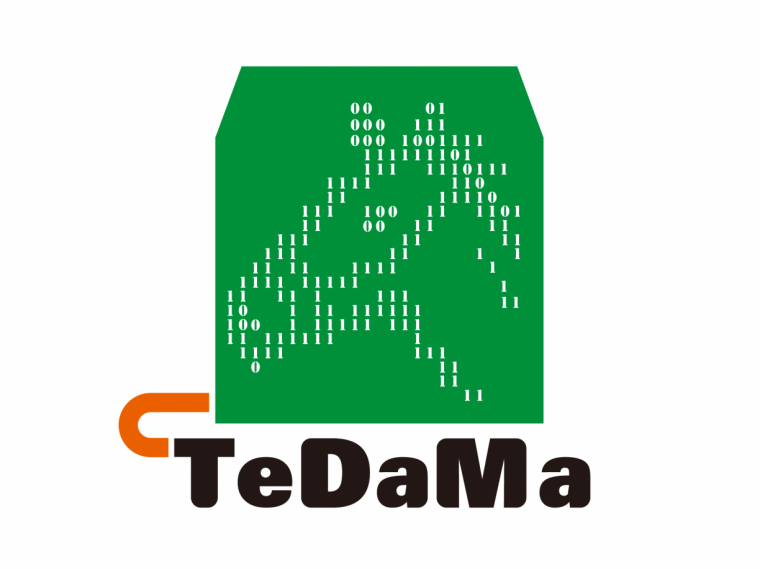

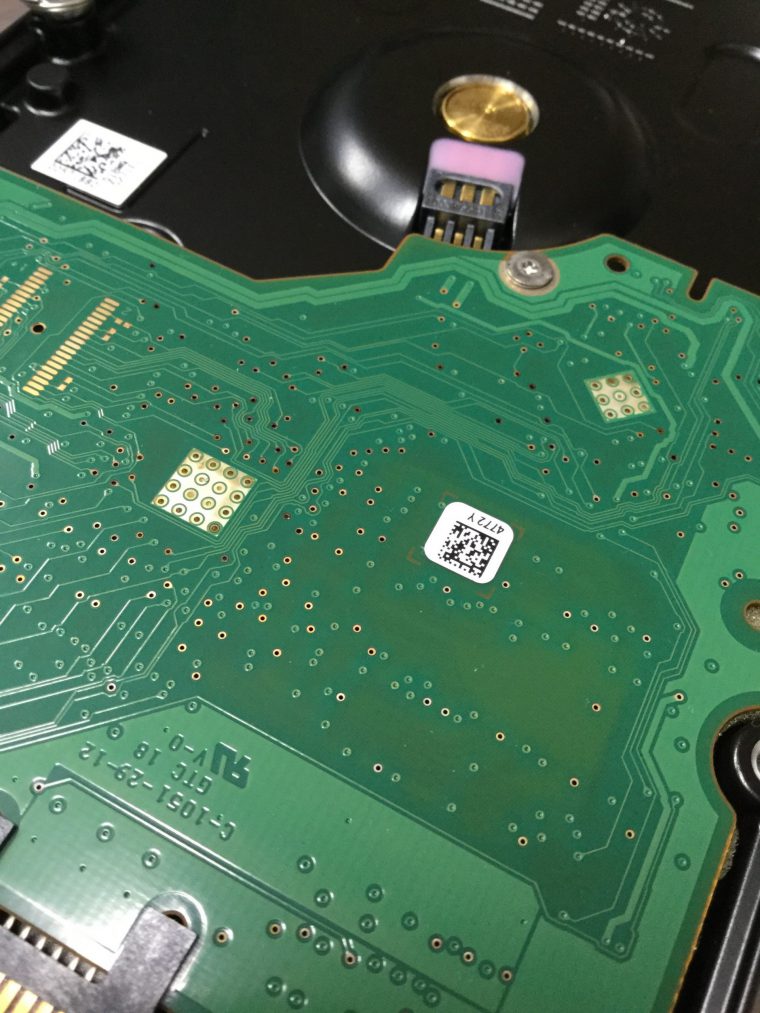

コメント