上手なヘルプデスク対応

データ入力マニュアルをどれだけ入念に作っても、利用者からの質問は容赦なく事務局・データセンターのヘルプデスク担当に降り注ぎます。ヘルプデスクで処理しきれない難しいケースがあると、ベンダーへ問い合わせが入ります。末端の利用者にとっても、ベンダーと利用者の間に立っている担当者にとっても、何かが上手く行かないというのはストレスが伴います。今回は、ここに焦点を当ててみたいと思います。
トレーニングはどのくらいすべきか…
臨床研究においても、自ら治験においても、使われているEDCはたくさんあります。一般的なオフィス用ソフトウエアと違い、参加施設の担当者がポチポチしているうちに何とかなる…というわけにもいきません。そのためにデータ入力マニュアルを作るのですが、人間それをメールで送ってもらったからってササっと実践できるものではありません。理想は、どこかでトレーニングの機会を設けることです。実環境のコピーを用意するなどして、実際に手を動かしてデータ入力を経験させることがベストです。
とはいえ、アカデミアが主導して行う研究は、基本的にリソースが限られています。日本の病院事情も関係して、目的症例数が数百例の規模でも参加施設が大変多くなりがちです。全ての施設を回ってトレーニングをするのも、逆にすべての施設の担当者に一か所に集まってもらうのも、どちらもコストが絡んできます。マニュアルを送ったうえで電話で説明しながら実際に手を動かしてもらう、動画形式のマニュアルを作成する、Webでトレーニングを開催する…等の工夫が必要になってきます。
幸い、紙媒体と比較して、EDCはあらかじめ変なことができない風に作られています。日付は特定の形式しか受け付けない、臨床検査値に全角で数字を入力しても受け付けない、間違った桁数を入力しても弾かれる…ですので、紙で運用していた時と比較して楽になった部分もたくさんあります。未然に防げない部分は、エディットチェックを駆使して入力内容に対して利用者に助言をすることも可能です。
データセンターでは対処しきれない場合
EDCが意図したとおりに動作しない等の問い合わせは、データセンターだけで解決するのが難しいです。ログイン画面でエラーが表示される、被験者の割り付けが出来ない、間違って追加した有害事象フォームが削除できない…。ベンダーに問い合わせをすることになるのですが、困っている利用者を待たせることになり、ストレスフルな状態です。ベンダーのカスタマーケアが正しく動作するには、大きな前提条件があります:報告されている事象の再現です。
スクリーンショットを撮ってもらう
ご存知の方も多いと思いますが、WindowsパソコンではキーボードのPrint Screen(Prt Sc)キー、Macintoshでは⌘+Shift+3を押すと、表示中の画面をコピーできます。その後、ペイント等の絵描きソフトを開いて「貼り付け」をすると、画像を保存できるようになります。あとはこの画像をメールに添付すれば、不具合の内容が伝わりやすくなります。
使用環境の情報を収集する
昨今のEDCは、使用ブラウザを問わず動作する(と謳っている)ものが増えています。とは言え、これは思わぬ弊害も生んでいます。ブラウザは、利用者が思い通りにカスタマイズできるものです。大手検索プロバイダーの○○ツールバー、ポップアップブロッカー、ブラウザのセキュリティ設定等の中には、EDCと相性の悪いものもあります。また、ブラウザ間で細かい仕様が異なる場合もあります。こういった不具合は、OS、ブラウザバージョン、そしてEDCのバージョン等の使用環境の情報が無いと、ベンダー側でも問題の再現が難しいです。
それでも再現に至らない場合
スクリーンショットや使用環境の情報でも解決しない場合もあります。データセンターにとっても、ベンダーにとっても、ストレスフルな状況です。原因は様々ですが、もっとも疑われるのが利用者のネット環境です。帯域の問題であったり、ネットワークの構成の問題であったり、稀ではありますがセキュリティの問題であったりもします(EDCによる通信を害悪と誤認してしまう)。この場合、解決には利用者側のITスタッフの協力が不可欠であるため、解決が非常に困難な場合もあります。また、原因が見つかったとしても、解決にはEDCソフトウエアの最新版へのアップデートが必要な場合が多いです(EDC一本のために参加施設側がネットワーク設定を変更することはまず期待できません)。対処方法はケースバイケースになりますが、解決が不可能な場合、モバイルルーターの使用や、サーバーの設置場所を移動したケースもあります(当然、これは最悪のケースです)。
一番大事なのはフローを作ること
問い合わせが入った→受領の連絡→調査待ちとして「問い合わせ箱」に移動→データセンターで対処できるか否かを判断→問い合わせに返信ORベンダーに助言を求む…といった具合に、ヘルプデスクのフローを作ってしまうことが推奨されます。プロセス管理ソフトがあればそれが一番良いのですが、それ以外の場合はエクセルの出番です。メール本文をそのままエクセルに貼り付け、回答内容も貼り付け、という習慣をつければ、しばらく経ってから似たような問い合わせがきてもエクセルファイルの検索ですぐに出てきます。多くのベンダーも、問い合わせがきたらまずやっていることは「類似の事例の検索」です。半年に一回のペースで出てくる、対処方法がちょっと複雑な稀な問い合わせの対策に特に有効です。






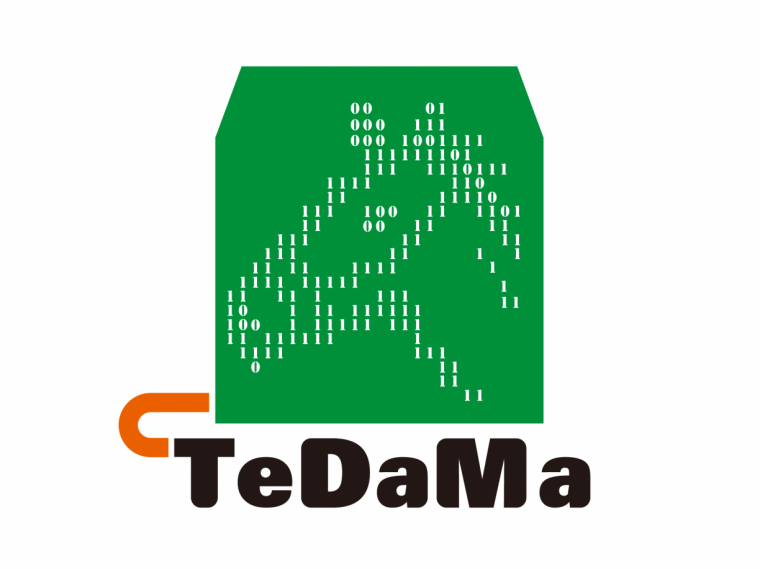

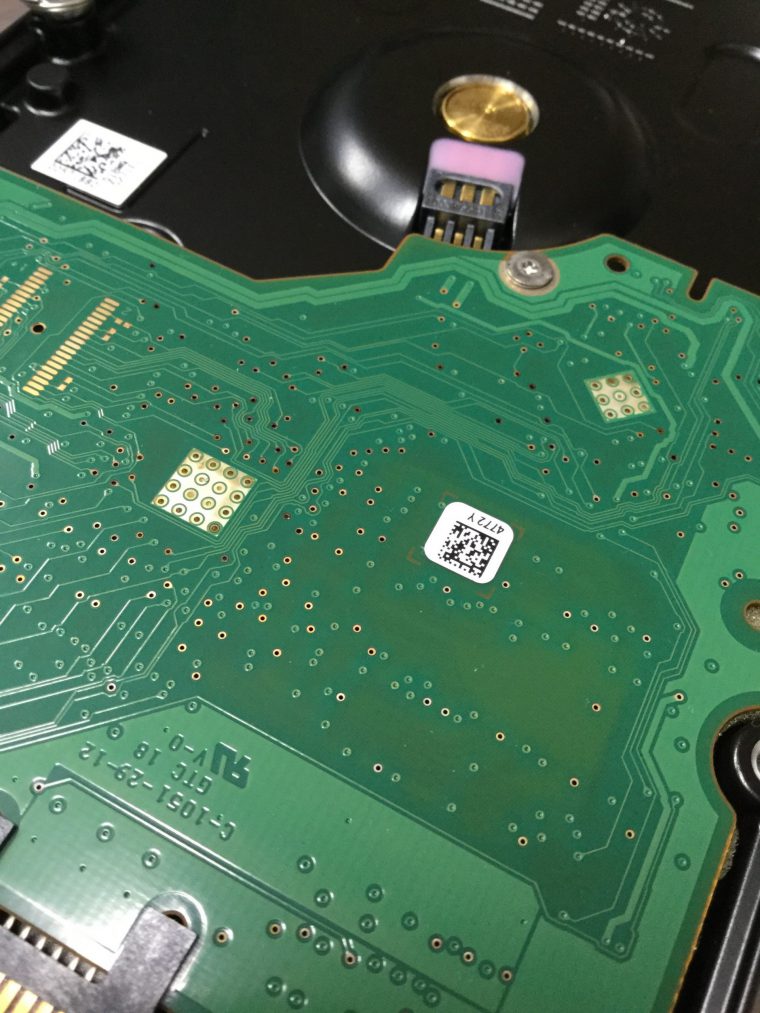
コメント