信じてもらえない正確さ

昔話です。日本の治験のオーバークオリティが叫ばれて久しいですが、最近めっきりその言葉を聞かなくなったように思います。日本がどうとか言う代わりに、世界的にリスクベースモニタリング等のアプローチが注目されているのと関係しているのでしょうか、はたから見ているとそのように感じます。
日本のオーバークオリティinオランダ
はじめて日本のオーバークオリティに遭遇したのは、オランダのライデン大学でまだ学生をやっているときのことでした。日本との国際共同早期臨床試験の責任医師に呼び出され、とある数値について意見を求められました。見せてもらったのは、血液検査の採血日時やバイタルサインの測定日時のデータでしたが、これが綺麗に2分間隔になっていました。
早期臨床試験に関わったことがない読者の方々が置いてけぼりになってしまうといけないので、この時点で補足:薬の効果を患者で「試す」前に、患者ではない、いたって健康な人に薬の安全を「確かめる」ことをします。そこで、多くの健康な人(いわゆる「被験者」、10人~20人程度)を一カ所に集めて、みんなに薬を飲んでもらいます。薬を飲んだ後に、薬が身体に吸収されているのを、採血をして確かめるのですが、すべての人で条件が同じになるように、服薬後同じ時間が経過した時点で採血をしたいわけです。ですが、20人に集まってもらって一斉に薬を飲んでもらったら、ぴったり30分後に採血するには、採血する人も20人揃えることが必要になってしまいます。そんなに看護師・検査技師を揃えるのは難しいので、服薬のところから一定間隔ずらします。太郎君は9:00に飲んでもらって、真之介君は9:02に、剛君は9:04に…といった具合に。そしてその後の採血も、その他必要な検査も一定間隔で、行います。太郎君の採血は9:30に、真之介君の採血は9:32剛君の採血は9:34…
さて、服薬だとか、採血だとかの実際の日時データだったのですが、これがすべてぴったり2分間隔になっていました。すべて、予定通りにことが進んだ、ということです。何が問題なのかよくわからなかったのですが「こんなに一度も狂わないなんて、いくらなんでもおかしいと思わない?」と言われ、一瞬、「おかしいですね」と言いかけたところで、ある光景が脳裏を過ぎります。子供のころテレビで見た日本の工場の映像です。日本から送られてきたビデオの映像だったと思うのですが、ロボット(超合金○○○)の玩具の部品を目の前にした作業員が、せっせと、寸分の狂いもなく製品を組み立てる様子です。速い、とにかく速い。ある程度まで組み立てたらトレーに入れ、またばらばらの部品が目の前に運ばれる。その繰り返しです。
あの作業員たちと同じ気質が、試験スタッフにもあったとしたらもしや…とは思いましたが、結局その場では責任医師に対して意見はできず、「う~ん…」と弱く頷くにとどまりました。
本当だった!
そして縁があり、日本で第Ⅰ相の仕事にかかわることに。看護師の方も、検査技師の方も、皆さん何やらストップウオッチを首から提げていて慌ただしく動いていました。とりあえず吸収しようとじろじろと見ていたら、突如と始まる号令、そして「被験者番号○○さん、採血30秒前」という謎のカウントダウン(タイムコールと呼ばれます)…。何が起きているのか最初は理解できませんでした。予定通りに服薬、採血、その他諸検査をすることに全力を注いでいる、そんな印象を受けました。これだけ几帳面にやれば、アクシデントでもない限りはすべて予定通りにことが運ぶのも頷けます。
被験者一人あたりのスタッフがオランダの現場よりも多いと言われたらそういうわけでもないのですが、オランダでは同じ服薬や採血をする前でも、被験者となにかしらのおしゃべりが発生します。「じゃ、そろそろ採血の時間だけど気分は大丈夫かい?」とか、「留置針はグラついていない?採血が今日この後8回もあるから肩の力抜いてね~☆」という具合に。採血ポイントのために看護師が病棟に入ってくるのを見て、「あ、トイレ!」と言ってそのまま採血が数分遅れることもありました。そんなこんなで採血時刻が数分前後してしまうことはしばしば起こります。基本的に、5%から10%程度のズレは、問題視されていませんでした。
戻って報告…そして議論
しばらくして、オランダに戻る機会があったので、当時の責任医師にも、「あの採血時刻の話、あったじゃないですか?あれ、適当に予定通りの時刻を記入しているのではなく、全部本当のことだと思われます」と報告をしました。タイムコールのことを話したら、最初信じてもらえなくて、漸く信じてもらえたと思ったら今度は大笑いされてしまいました。
「でも、凄いですよね、正確に超したことはないってことで」と言うと、責任医師は少し考え込んで、「あたしは懐疑的、無駄な努力だとさえ言いたいわ」とばっさり。「だって、その正確さを追求する過程で、ほかのところを捨てるしか無いわけでしょ。そして、それに力を注いで得られた分単位の正確さに意味があるとは考えにくいし」と続けました。検証を行って、その上で5%だとか10%だとかのズレは誤差範囲、という結論に至っていると言う。確かに、正確さの追求にはキリが無いし、分単位どころか秒単位で服薬90分後にドンピシャで採血をしたところで、データとしては1.5時間後のデータですからね…
ちなみに戻って逆に報告をしたら、「できることをせずに、正確さを【あえて】欠くことの合理性が逆にわからない」という意見も多かったです。日本の現場スタッフとしては、タイムコールで無理をしているという意識はなく、採血する者と、採血管を確認する者と、どのみち二人で回るならタイムコールするくらい苦でも無い、という考えです。どちらが良い悪いかというより、オランダは被験者の快適さを追求していくうちに、ある程度の「ズレ」は許容することが「自然」となったのに対して、日本では技術的な正確さを追求するにあたり、どうせだったらタイムコールもやろうか、というのが「自然」だっただけかも知れませんね。

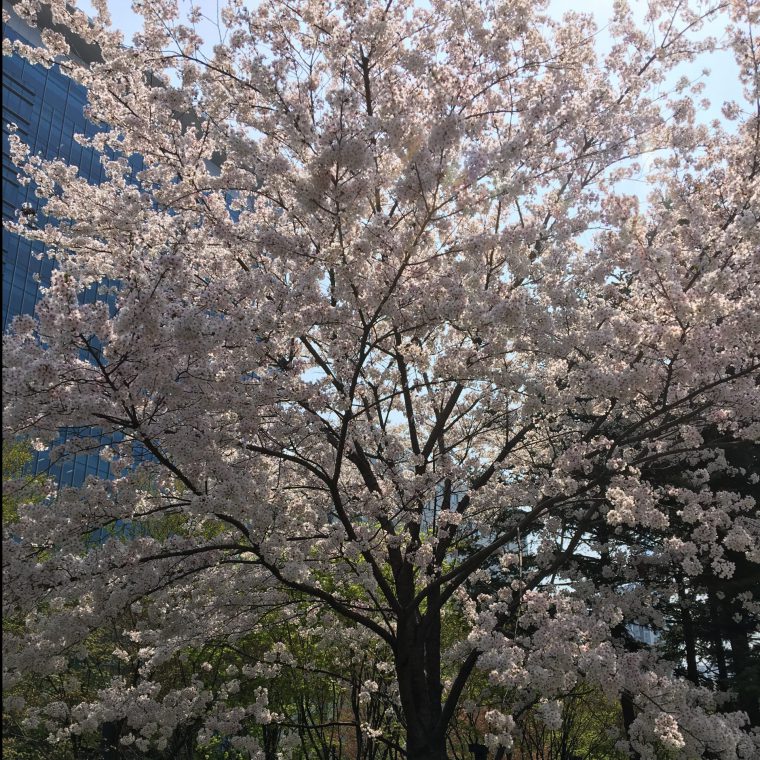


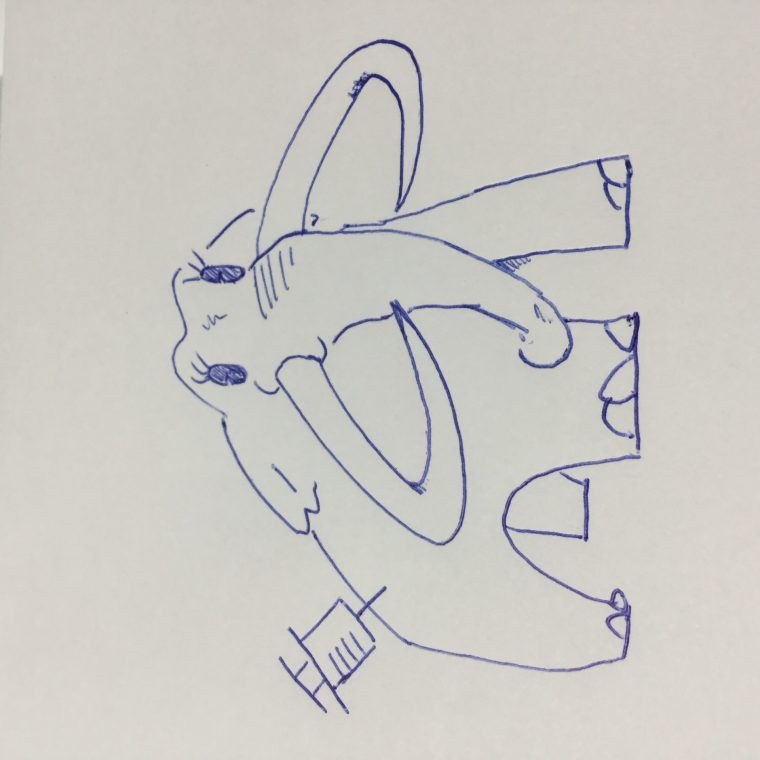



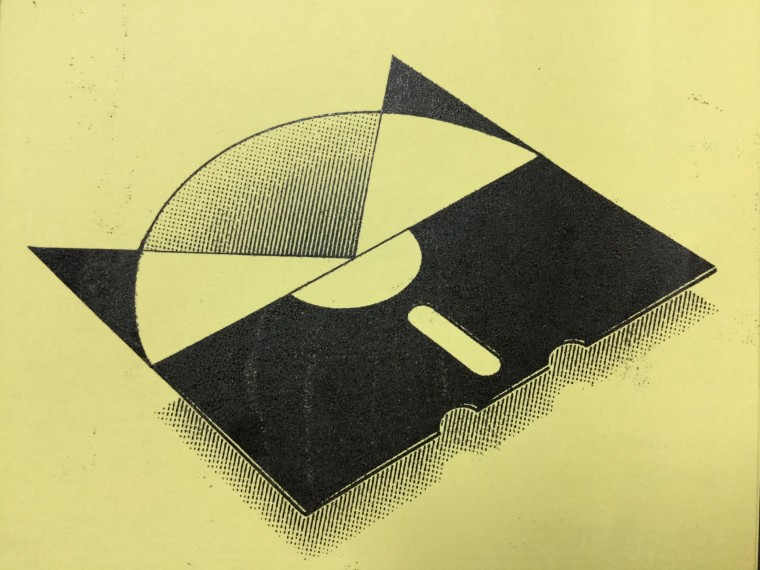
コメント
コメント一覧 (2件)
日本のオーバークオリティはやはり問題だと思います。お話の事例はPhase1なので「きっちり」と思ってスタッフはやっているのでしょうが、どの試験も同じに「きっちり」やろうとするのは問題だと思います。
品質にこだわる日本人気質がリスクベースドモニタリングのブレーキになっているように思えるからです。
人なんだからミスしてもあたりまえなのに、その妥協が許されない風習が実働の人たちのプレッシャーにつながり、責任の押し付け合いをし合っているように思えます。
もっとメリハリを持ちたいですね。
今は医療職ですが学部生時代に臨床薬理の臨床試験(治験ではないです)で薬物動態の研究に被検者として参加しました。タイムコールでしっかりやってるのをみて、すごいなあと思って試験に参加した記憶があります。被検者としてはきっちり管理されるのはあんまり不快感はなかったです。実際の患者に対する日常診療での薬物投与/薬物血中濃度測定は、他の患者の対応などで予定通りにならないことは多いですが、それにくらべれば急変や突然のトラブルも少ないですし、あんまり苦もなく採血をタイムコールでできるような気がします。ちなみに5~10%の誤差というのはもともとプロトコールに書いてあるものなのでしょうか?Phase 1 studyをしらないので実際のところが気になりました。最初から誤差okとあれば、また日本での対応は違ってくるように思います。