訪問型モニタリングは果たして減るのだろうか

ICH E6のR2がステップ3~4の間を宙ぶらりんしている今、リスクベースドアプローチと言うキーワードは大流行期を迎えています。EDCに関して言うと、とりわけリスクベースドモニタリングと、中央モニタリングがホットな話題です。尚、パブコメが締め切られたのが1月15日ですが、開示はいつごろになるのか、厚生労働省医薬・生活衛生局審査管理課に問い合わせてみても、何ともお答えできないとのことですので、首を長くして待っている状態です。なんか、こう、ロードマップでも出してくれればソワソワしないで済むのだが、まさかお役所も全く何の目標も立てずにただひたすら仕事しているわけでもあるまい(少なくとも、そう思いたい)。
さてさて、リスクベースドモニタリングについてです。こちらのブログでもたびたび話題にしておりますが、強烈な金食い虫である施設訪問をした上での直接閲覧(訪問型SDVとでも)と、比較的少ない労力で実装できるエディットチェック・オートクエリは、ほぼ同じ数のエラーを検出できるとする結果があります。前者は人力、後者は(設計はもちろん人力だが)基本的にオートメーション。前者は費用効果という意味での効率が悪く、更なるクオリティアップを目指すには膨大な投資が必要なので、困った子です。となると、後者の、費用効果が良くて、伸び代も工夫次第でいくらでもありうるという方に考えがシフトしていくのは自然だと考えられます。一つの見方としては、エディットチェックやオートクエリは従来訪問型SDVでしか検出できなかったものを、訪問しないでも検出できるようにしたものです。
ここでちょっとわき道にそれますが、「オートクエリ」と聞くと、CRCの方々は嫌な思い出がたくさんあると思います。CRFのページを保存した途端に、それまでは落ち着いた寒色系だったパソコンの画面上に映し出されたEDCの様子が一変し、フォームのいたるところに赤ペンが入ります。そして修正させるだけでは飽き足らず、修正理由まで項目の一個一個に対して要求してくる。「修正しろって言われたから修正しているのに、何ですか修正理由って?しかも同じページで5回も!」と、CRCが不満をぶつける先はモニター…ですがモニターも誤るしかできず「すみません、データマネジメント部が強くて、我々にはどうにもできないのです…」と。私自身も、修正作業に追われ、発狂しそうになる日(正確には夜)もありました。
エディットチェックやオートクエリの実装方法には大きな問題があり、EDCベンダーも依頼者もともにここは責任があると感じております。更なるオートメーションを推し進めることは、こういう苦い経験を繰り返ししてきた「現場」にはなかなか受け入れられるものではないということも、もっと自覚すべきだと思います。リスクベースドモニタリングの話が出始めたころ、「まーた実施施設に押し付けて自分たちだけ節約しようとしているよ!」と思われた方々は多かったのではないでしょうか。その後の業界団体等による情報発信の甲斐もむなしく、現在進行形でもこのイメージはまだ拭えていないと感じる方々は多いです。実施施設のみならず、受託機関においても、同じ理由からリスクベースドモニタリングに懸念を抱いているところもあります。この場合、自分たちの「仕事がなくなる」という懸念からではありますが。
ですが、リスクベースドモニタリングの目的は、モニタリングの費用を削減することでも、実施施設に煩雑な操作を押し付けることでも、無いです。とらえ方は様々ですが、一つに、費用効果の悪い方法に人員を割いている現状を、改善し、そこで手が空いた人員にもっと有意義な作業にあてる、ということだと思います。これは、税金と言う名のつかない税金が大きな収入源になっている企業としては、もはや社会的責任だとも思います。
更に言いますと、正直、訪問型SDVが減っても、訪問型モニタリングが激減するとは考えにくいです。少なくとも今の日本で、すぐには。国外で一定の成果を出しているリスク指標がそのまま日本の実施施設に当てはまるかは、まだまだ検討が必要でしょうし、そもそもベースにある臨床試験に関する知識レベルも米の平均的な病院と日本の平均的な病院とでは差があるでしょうから。ですが訪問した際に、カルテ庫にこもるだけでなく、もっと有意義なことに時間が割けるようになるとは思います。責任医師、分担医師と話して、問題点を分析して、例えばエンロールの目標を建てる。CRCやナースと面会して、CRFの記入で困っていることは無いか、再トレーニングの必要性は無いか、等を確認する。機械的に処理するだけのモニタリング業務の比重が少しずつ減っていき、本来あるべき姿のモニタリングが増えてくれればと思います。その方がモニターにとっても、よりやりがいのある業務内容になっていくのではないでしょうか。






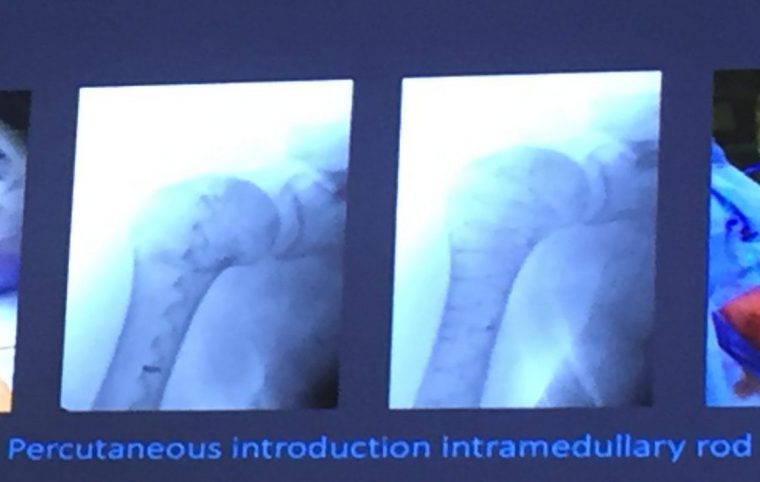


コメント