第37回日本臨床薬理学会学術総会2日目

昨日のシンポジウムはギュウギュウ詰めで、座る場所場無く立ち見する方々も見かけられました…毎度のことなのですが、ホールが大きすぎたり、逆に小さすぎたり、なかなか難しいものがあるみたいですね。事前登録者に、どのシンポジウムを拝聴したいかアンケートを取った上でホールの振り分けを考えても良いんじゃないかな、と素人目線で思った次第です。さて、「IRBの脱施設化はどこまで可能か」は、内容的には満足できるものでした。どうしてもモヤモヤしてしまうのが、総論賛成なのに(だと主張するのに)、何故動きがこんなに遅いのか、ということです。倫理審査は、少なくとも一国の中では普遍化できるものでなければならないはず。施設毎に審査すること自体がおかしい、と思います。と、また持論展開しても直前の投稿と被るのでこの辺で。
今回、発表内容からオランダの倫理審査体制はリストラされておりましたが、是非参考にされたい、と感じています。以前にも書きましたが、オランダも昔は日本と然程変わらない状態です。かなり強引な手法で数を減らし、倫理審査委員会の認定制度を設け、今の状態にあります。ちょっと整理して、また将来記事にします(蕎麦屋になりませんように…)。
今日はポスターをメインに見て回り、アカデミアでもポツポツとRBM(リスクベースドモニタリング)の検討を始めていることです。脱線しますが、RBMのことをリスクに基づくモニタリング、外来語と日本語を絶妙に織り交ぜた言い方もあるが、私は好きになれません…日本語入れるならリスク依存型モニタリングかな、と思います。夕刻のシンポジウムは、「なぜ日本では臨床薬理学を医学教育・研修医研修に組み入れないのか?」というトピック。理由は、私もこれは長らく疑問に思っていたからです。オランダの医学部バイオメディカルサイエンス科は、多くの授業が医学部医学科(要は、医者さんになるための方)と一緒でした。薬理学には十分な時間がカリキュラムで割かれており、その中で臨床薬理をちょこっとだけ扱います。が、それだけです。
私も最初の就職先で、オランダの南のOss(旧オルガノンがあったところ)というところで三日間、臨床薬理の基礎を学びました。早期臨床の実施を生業にしている施設であったため、直接被験者・患者に対する手技に関わらない自分でも、最低限の知識がないといけないという理由からです。今となっては錆び付いていますが、被験者の採血のタイミングをメーカーと協議する上でも、複数の被験者の採血と特殊検査のタイミングが被ってしまった場合にどちらを優先させるべきかの判断にも、この基礎は欠かせなかったです。
臨床薬理を必修にすべきかどうかはわかりませんが(ベターというのは疑いの余地はないですが)、臨床研究に絡める系統の基礎は盛り込んでも良いのかなと思ったりはします。前回の記事の認識論もそうですが、コホート研究を自分で考えようとか、疫学とか、データベースの授業とか、そういったトピックがライデン大学の医学カリキュラムには広く浅く仕込まれており、全体として医師・研究者の、臨床研究に対する興味をそそるのに機能していたのではないかな、とは思います。
と言いますか、また受けたい。社会人になると、多いですよね…また受けたいって思う授業。

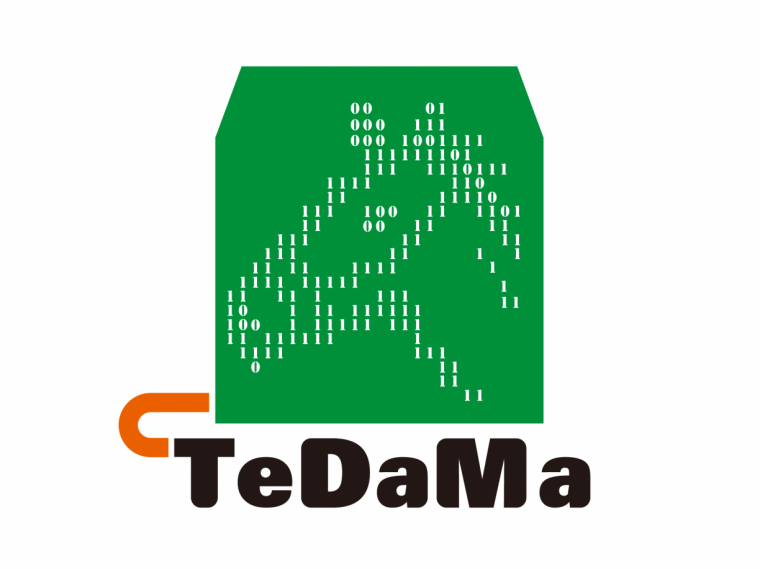
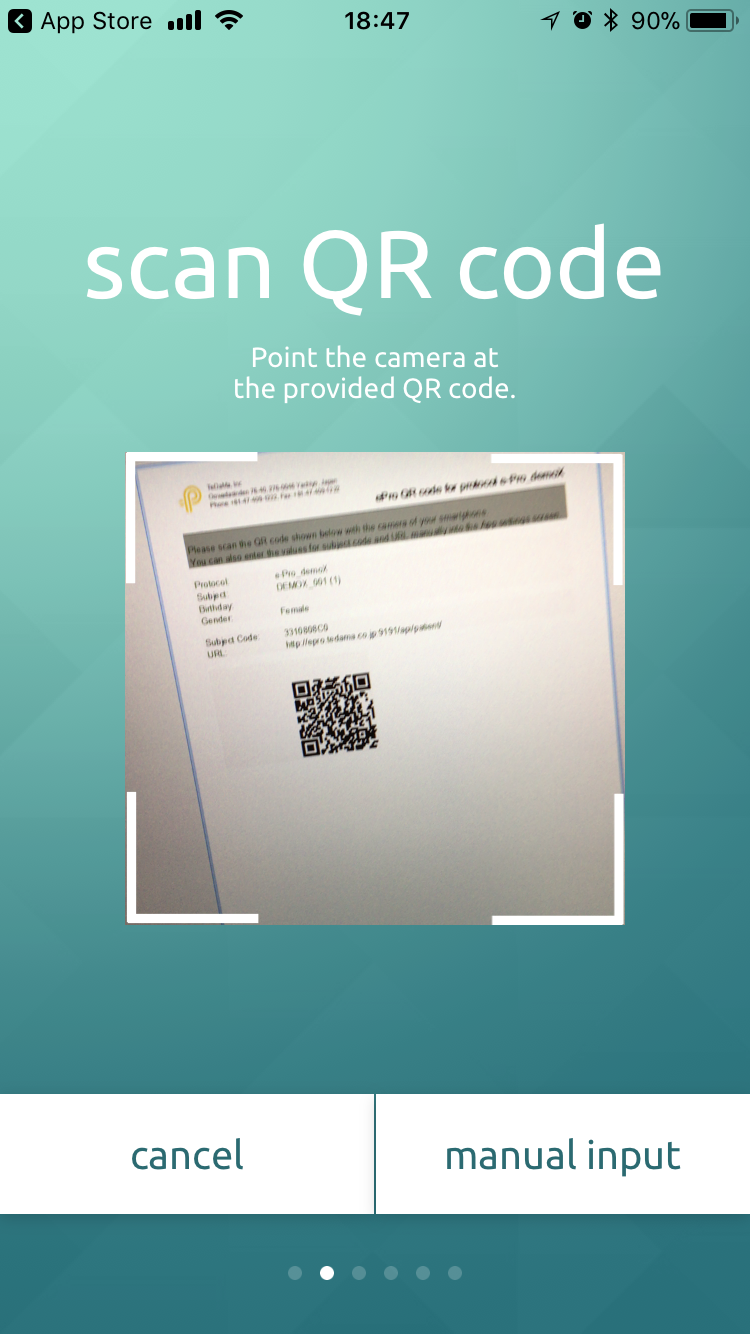

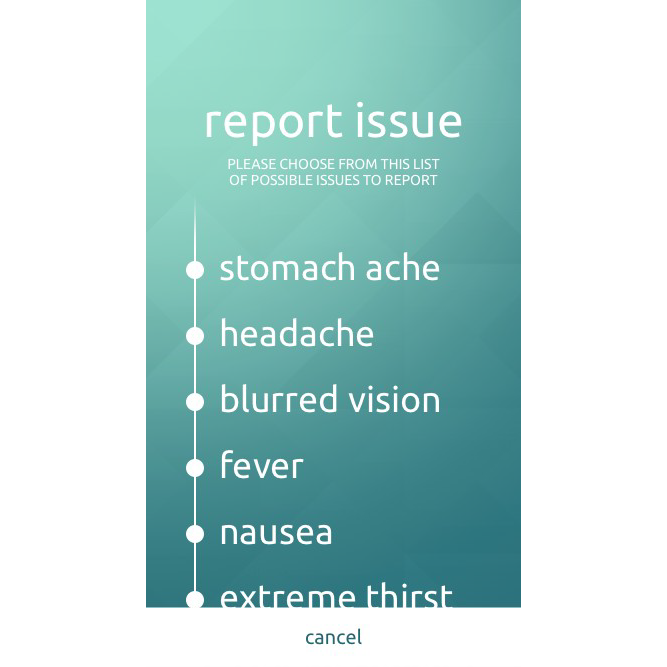
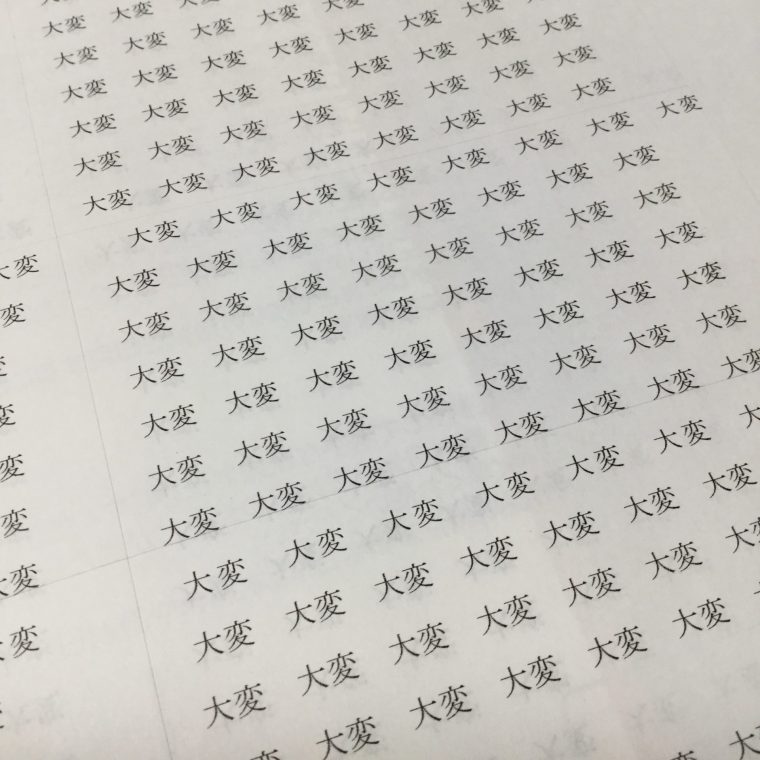
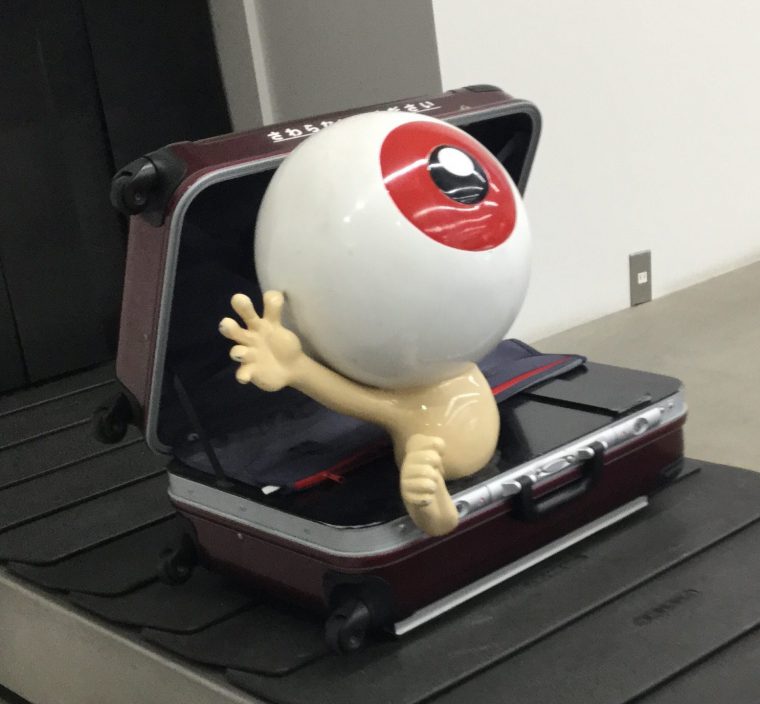
コメント