期待されるサービス
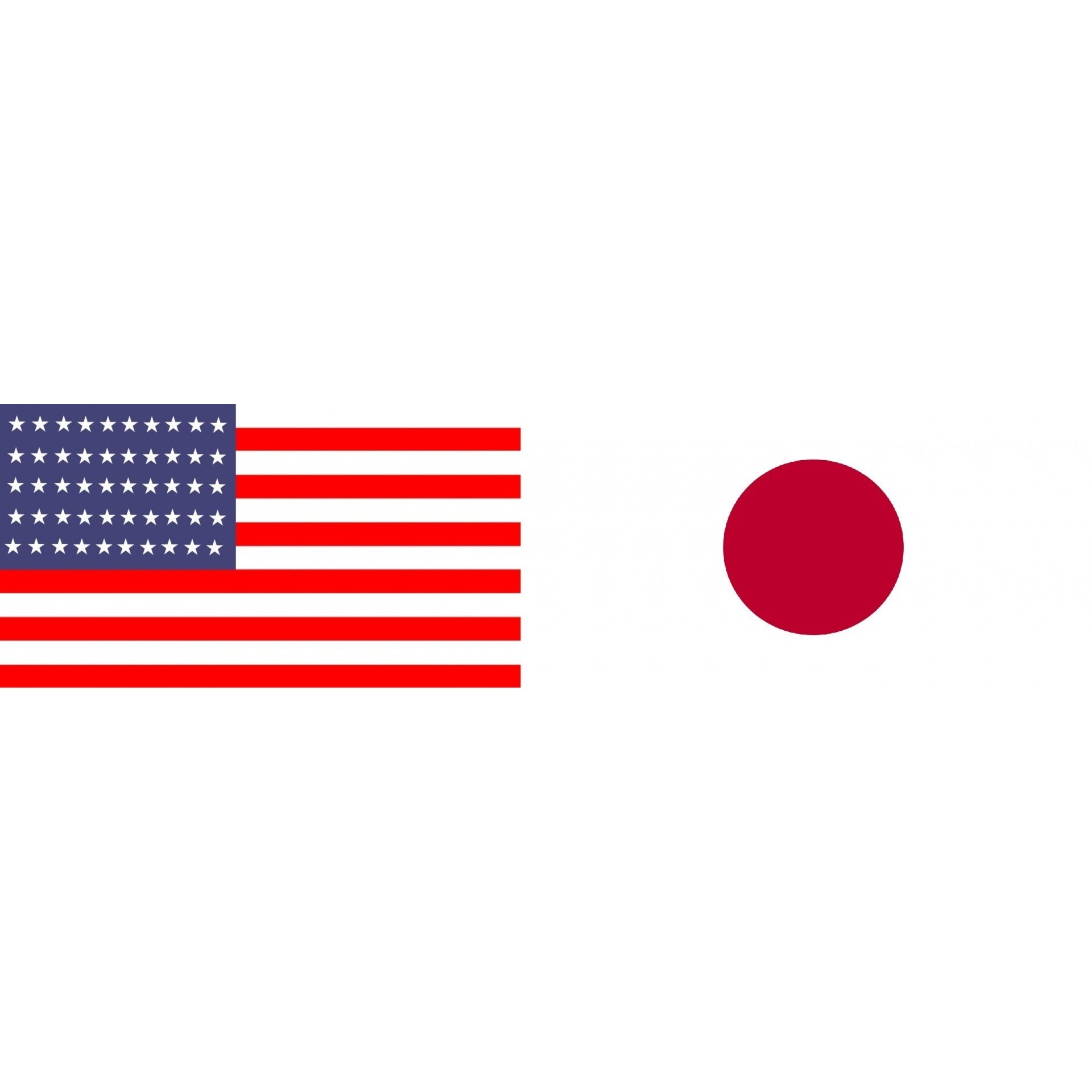
先日、新しいサービス体系について顧客に紹介をしたい、ということで、とある外国の方の通訳をさせて頂きました。担当者が丁寧にサービス内容を紹介し、いくつかの文節ごとに僕の方で通訳をしていた。内容としては、プラス料金で、通常のヘルプデスクよりも手厚いサービスを受けられるというもの。通訳の面白いところは、相手のリアクションが通訳されている側よりも先にわかってしまうこと。通訳をされている側が日本語を知らないからというのももちろんそうだが、言葉に出さずとも通訳をしている最中にも相手の表情でどう思っているのかはある程度わかる。担当者が説明を終えると、予想通りの返答があった:「そのくらいのサービスは、日本だと通常サービスの範囲内だと思うのだけど…」。
そのくらい当たり前
期待されるサービスレベルは国ごとに違う。どちらかと言うと、日本は「手厚い」というのが「標準」になっていると感じる。月に一度は顧客に連絡をし、現状について確認をする。お客さん毎に、お客さん特有の状況をしっかりと把握し、サポートに電話した際も把握しているメンバーが応対する。EDCベンダーの場合で言えば、お客さんから電話がかかってきたら、今そのお客さんでどのプロトコルが走っているのかを把握して、技術的な質問なら状況にあった返答をする(観察研究を実施しているのと、自ら治験を実施しているのとでは同じ質問でも答え方は異なる場合もある)。試験特有の質問についても、一般論で答えなければいけない。国外の企業にとって、これを一般のサービスとして提供するのはなかなか厳しいものがあるのだろう。
労働生産性の低さと表裏一体?
少し前に、ハフポストの記事「日本の労働生産性が低い、14の理由 「もっと頑張る」以外の解決方法は?」が色んな所でシェアされていました。記事の著者も指摘されている通り、特段話題としてのノイエスは無いと思いますが、挙げている14の理由の説明が簡潔でわかり易いです。でも、同時に激しい違和感もあります。「何と比べて」というのもそうだし、「解決したらまともになるの?」というのがはっきりとしない。生産性ばかりを重視した「供給」を市場が求めていないのであれば、会社の労働生産性を上げることは、内需を切り捨てることにつながりかねないか、という疑問もあります。ハフポストの記事の内容どおりに日本のやり方にすべてメスをいれたところで、果たして日本で要求されるサポート体制が維持できるのだろうか。日本人の「働く姿勢」と「働き方」が全くリンクしていないとは、私にはとても思えないです。お客さんを大事にするから残業をする、流動性が低いからお客さんとの関係性が深まる、相手を責める前に自分に非が無いかを考えるから鬼上司が生まれるスキを作る…悪いところだけ切り取るのは難しいのではないでしょうか。
グローバル化が生む悩み…?
一つの製品をグローバルで提供するということは、世界どこも、同一対価で同一サービスが提供されるというのが理想とする声もある。従って、この場合は先の紹介にもあったように、日本では一般的にに「普通」とされているサービスレベルも、「別料金」ということになる。その姿勢を貫いて成功している大きな企業もありますが、そのような強気な姿勢に出られるのは、よほどのブランド力があるか、自分の製品がよほどユニークであるか、等のファクターがあるのだろうな、と思います。お客さんが文句を言いながらも、自社の製品を使い続けてくれる状態にあるという企業(その道の専門家ではないのであくまで想像ですが)。それ以外のベンダーさんは、サービスに関しては、やはり自分たちで何とか「勉強」しなければならないのでしょうね。






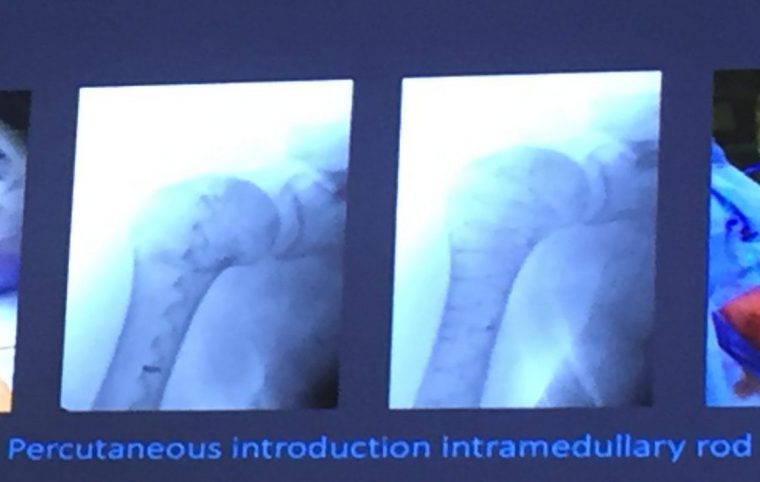


コメント