紙CRFからEDCを起こすとき
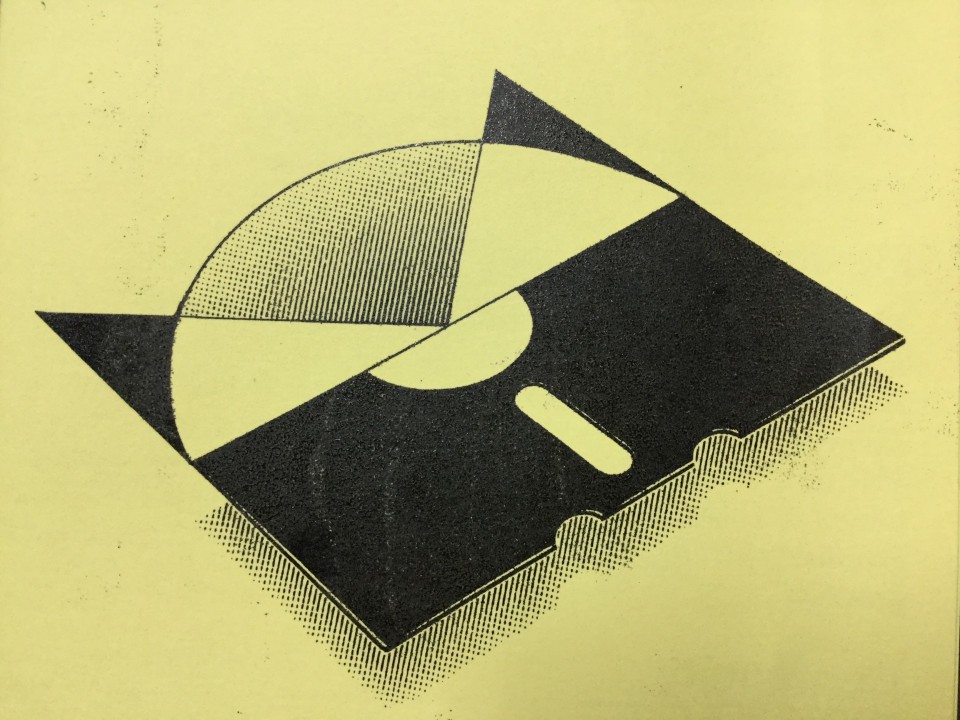
臨床研究であれ、自ら治験であれ、緊急の依頼がある場合は紙CRFがもう出来ている場合が多い。昨今、EDCというものは、データベースデザインから紙媒体のCRFを出力できるものが多いので、もったいないと思う反面、集めたい項目の一覧が出来上がっているので、EDC構築はちょっと楽になるのも事実。先日、見積もり依頼とともに頂いたCRFのサンプルをベースにサクっと組んでみると、4~6時間くらいでそれっぽいものが出来上がった。プロトコルをなぞって作るよりも、はるかに早いことは否めない。ただ、「紙ならでは」を盛り込んでくることが多く、そこはどうEDCに落とし込むか悩みます。「紙ならでは」と言えば聞こえは良いですが、いずれ電子化して解析に回さなければいけないもの。「紙ならでは」は、解析担当泣かせとイコールの場合が多いと感じています。少々駄文になりますが、今回はそれについて…
桁数がわからない
紙CRFで数値データ(臨床検査値等)の記入欄には、ほとんどの場合桁数の指定がありません。電子化するにあたって桁数が重要なだけでなく、紙媒体で収集する場合も桁数を明記しないのはあまり宜しいやり方ではないと感じています。多施設共同試験で起こりうるミスなのですが、同じ項目もとある施設の検査伝票では単位が10^4で表示され、別の施設ではこれが10^3で、また別の施設では0がゾロゾロ付いた標記になっています。電子化抜きにしても、間違いを産みやすいので、紙媒体でも桁数の明記は推奨されます。

紙媒体でも桁数を示すことは重要
複数選択
複数選択…EDCによって、対応している・対応していないがあります。ですが、いずれの場合においても、複数選択というのは解析前には何らかの方法で2値変数に分解しなければならなくなります(CDISC標準においても、一つの変数に複数の値を格納してはならない、とバッサリです)。また、複数選択のデータ品質上の大きな難点は、「チェック漏れ」と「チェック無し」の区別が付かないことにあります。選択・除外基準においては、この原則は広く受け入れられていますが、何故か臨床データだとどうしても複数選択が魅力的に感じられてしまうものです。ですが、正直電子化の話を抜きにしても、あまり良い集め方だとは思いません。

背景因子として使うならどの道2値変数への変換は必要…
予め複数用意された記入欄
既往歴、合併症、併用薬、有害事象等々、記入欄・入力欄がいくつ必要になるかわからないものは、紙媒体では予めいくつかの記入欄を設けておくことが多いです。これをEDCでもやってしまうと、データセットに空欄が多く残ることが懸念されるので、基本的には追加フォームでの対応、あるいはEDCが対応している場合は、その場でEDCに必要な数だけ入力欄を挿入、というスタイルになります。いずれにしても、紙媒体とはどうしても使用感が大きくことなる部分であり、構築時もそうですが、EDCをはじめて触る方々に対してのトレーニングをどうするか、ややこしいです。
ややこしい分岐
紙媒体ではチェックボックスと矢印を駆使して複雑な分岐が行えますが、EDCでは、複雑なエディットチェックを組むはめになります。紙媒体のややこしいところは、こういった分岐が正しく行われているのも全て目視でチェックせざるを得ないところです。その点、EDCではエディットチェックで間違った分岐をしている場合にアラートを鳴らすことや、システム次第では入力欄の表示・非表示やグレーアウトなどが可能です。紙媒体の矢印をEDCに落とし込むのは大変な作業ですが、現場からしたらEDC導入の恩恵がもっとも感じられるところの一つだと思います。
結論:紙媒体も電子化を視野に!
解析をコンピューターで行わなければいけない都合上、どこかの段階で臨床試験データは電子化されなければいけません。EDCであれば、解析のし易い様にデータ収集フォームを作成することを半ば強制されておりますが、紙媒体だとそこんところが自由なのが、難しいところです。解析のし易さまで考えて作られた紙CRFが理想ですが、これが「ストン」と落ちるには、実際に解析の経験があるか、EDCまたはCDMSを組んだ経験があるか、のいずれかは必要だな、という印象です。


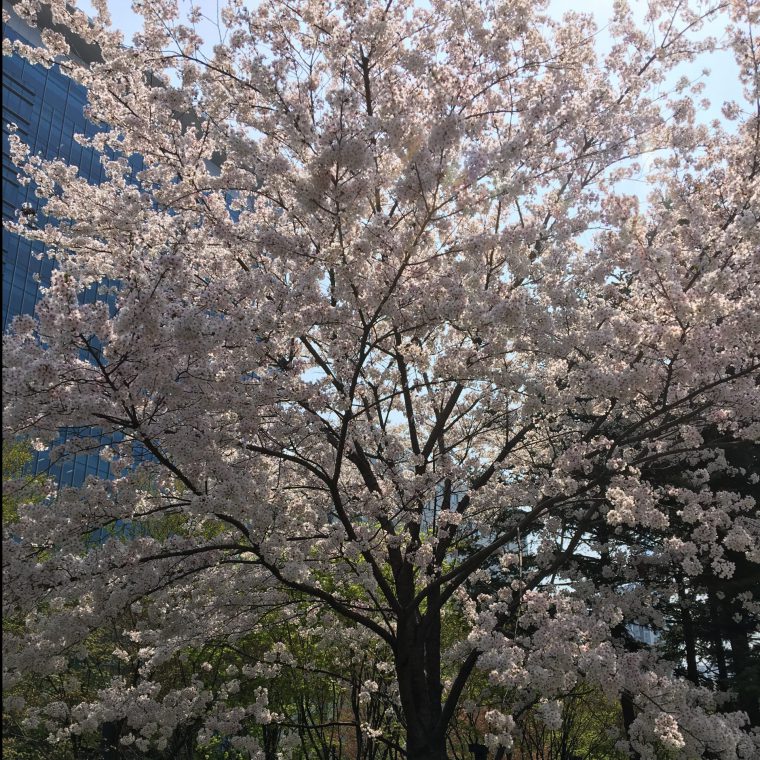



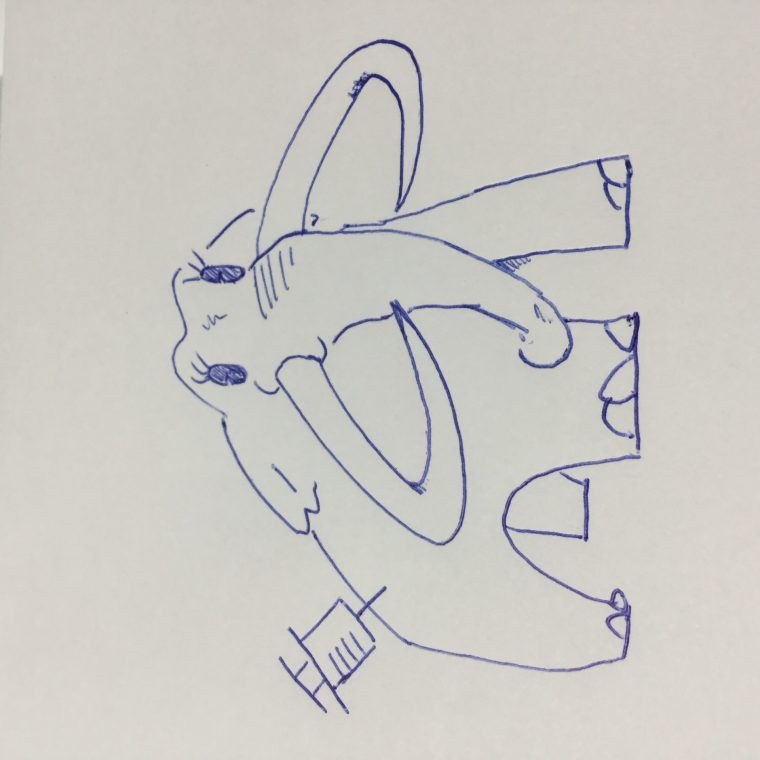



コメント